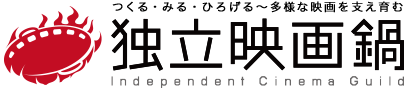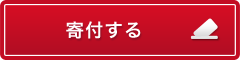鍋講座vol.49「デザイナーが解き明かす!映画宣伝美術の秘密」レポート―コミュニケーションが生まれる距離感を考えること―
「宣伝美術」この言葉に聞き馴染みがない人もいるかもしれない。ネット上で調べてみると、次のような定義づけが見つかった。
宣伝美術:応用美術のひとつである商業美術に属します。商業美術は商業を目的とした制作物を指しますが、特にディスプレイやチラシ・ポスターなど、何かを宣伝をするためのものを宣伝美術と呼びます。
*東京国立近代美術館「純粋美術と宣伝美術」展示を読み解くキーワードより引用
一般的には主に舞台、演劇そして映画の販促物がこれに該当する。この鍋講座では「映画宣伝美術の秘密」と題し、映画宣伝のデザインにスポットを当てた。これは49回目となる講座でも初めての試み。ゲストに映画の宣伝美術を数多く手がけている、気鋭のアートディレクター/グラフィックデザイナーの寺澤圭太郎さんをお招きし、デザインを手がけた事例を取り上げながら、発想から制作に至るまで、参加者との質疑応答も交えてたっぷりと話をうかがった。聞き手は独立映画鍋の会員であり、自身も映画の宣伝美術を手がけるグラフィックデザイナーの鈴木規子、司会は独立映画鍋の共同代表である映画監督の土屋豊が務めた。このレポートでは、寺澤さんが語ったデザインの作業過程と創作のポイント、その一部を要約してお伝えする。
宣伝美術は映画のイメージづくり
寺澤さんは「映画の宣伝美術とは何を指すか」というに問いに、「いわゆるメインビジュアルと呼ばれるもの。映画のイメージづくり」と答えている。それはポスターを中心とした、世の中に多く出まわる宣伝ビジュアルをデザインすること。そしてポスターに限らず、チラシ、試写状、前売り券、パンフレットといった紙媒体の形に落とし込んでいく。
そういった作業のやり取りは、基本的には宣伝あるいは配給の担当と行うのだが、監督が自ら加わることもあるという。打ち合わせに参加する人は作品によって様々。映画のどの部分を推して売るのかヒアリングを重ね、それを受けてデザイン案を作成し、宣伝、配給、さらには上映劇場からも意見を吸い上げ仕上げていく。時にはメインビジュアルを20案くらい作成することもあるらしい。全部提出する場合もあれば、提出しない場合もあるが、発注側とコンセンサスを取るため、あるいはこんなことも考えられるという打診の意味を込めて、複数案を提出するそうだ。
まずはコピー、ことばの大切さ
「ビジュアル作りは、感覚的に構築していく部分に加え、ロジカルに考える部分もあるので、ことば(コピー)に伝えたいことを集約するのはとても大事なことです」
寺澤さんは、最初の打合せにおいて、作品のキャッチコピーが決まってない場合は、仮でもいいから決めもらうように伝えるという。デザインを考える上でガイドラインになるからだ。
今回、事例として挙げた映画のコピーは印象的であった。例えば、『佐々木、イン、マイマイン』(20)の「佐々木、青春に似た男」、『アルプススタンドのはしの方』(20)の「そこは輝けない私たちの ちょっとだけ輝かしい特等席。」というキャッチコピー。これらのコピーには説明的な要素が少ない。それゆえ受け手に一瞬、考えることを促し、何らかの情景を想起させる。デザインの方向を定める上でも、大きな指針となるに違いない。
写真を選ぶこと、撮ること
「写真には説明的なものと、説明的でないものがあります。これは説明をしていないが、ちゃんと表現されているとてもいい写真だと思います」

青春時代のきらめきと、愛しい日々への哀愁を描いた『佐々木、イン、マイマイン』。その宣伝ビジュアルで使われた写真は、キャッチコピーとも相まって、何とも言えない雰囲気を醸し出している。特に印象的なのが、ティザービジュアルの佐々木を演じた細川岳さんの写真だ。ブレて、ボヤけて、そして顔が見切れている、その勢いがある画は、佐々木というキャラクターが持つパワーを的確に表現しているという。打ち合わせには、監督、キャストで原案を書いている細川さんも参加している。監督の熱量が高く、そして同世代のキャストやスタッフたちと共に作り上げたという意識が強かった。ティザービジュアルを作ることは、打ち合わせの最初の段階で決まり、写真の選択も寺澤さんと監督の意見がその場で一致した。基本的にいい写真が多く、選ぶのが楽しかったそうだ。
寺澤さんは『佐々木、イン、マイマイン』のデザインで大事にしたことについて問われ、こう答えている。「空気感です。写真でかなり表現されている。コピーも秀逸で、意味がないようで意味があります」
『百円の恋』(14)の宣伝ビジュアル、バンテージを巻いた安藤サクラさんの姿が印象に残っている人は多いだろう。「呆れる程に、痛かった。」というキャッチコピーがつくその写真は、恋とボクシングに目覚めていくヒロインの姿を、安藤さんが見事に体現している。寺澤さんはそれを「安藤サクラ力」と称賛した。

撮影期間中の休みを使って、寺澤さんの立ち会いのもとスチール撮影が行われた。(撮影を手がけたのは安藤サクラさんをよく知るカメラマン)寺澤さんがイメージとしてカメラマンやスタッフと共有したのが、タバコを咥えたシャルロット・ゲンズブールの写真だ。安藤さんが演ずるヒロインも映画の中でタバコを吸っている。メインビジュアルでは、安藤さんがバンテージを巻いた手で頬杖をつき、灰が落ちそうなタバコを咥えている。ボクシングのバンテージとタバコ。一見、矛盾している両者の組み合わせが、一度見たら忘れられないイメージを生み出している。
「決めて撮ればいいものが撮れるわけじゃないタイプの写真なので、ざっくりこのシャルロットの感じがいいと思うんですよね。というところです」
本作の場合、デザインのいわゆるラフは作らずに撮影に臨んだという。クライアントワークではラフを作ることは多いが、それには良いところと悪いところもある。「ちゃんとコンセンサスを取った上で、現場でこういうものもやってみましょうと、プラスアルファが生まれるのが良い」と寺澤さんはいう。撮影ができる場合はできるだけ立ち会い、現場に行けない時はリモートでチェックすることもあるそうだ。
イラストを使ったビジュアル
映画館「川越スカラ座」を舞台にした『銀平町シネマブルース』(23)のメインビジュアルではイラストを使っている。様々な登場人物たちが劇場の席にいる、とても賑やかなものだ。描いたのは、映画はもとより幅広いジャンルで活躍するイラストレーターの岡田成生さん。早い段階で配給・宣伝の方からイラストを使用したい旨を伝えられ、寺澤さんが岡田さんを推したそうだ。(寺澤さんは以前『街の上で』のパンフレットで岡田さんにイラストを描いてもらっている)配給・宣伝の方から参考資料として上がったのが、イラストによる『アニマルハウス』(78)と『ロックンロール・ハイスクール』(79)のポスター。その楽しげなイメージに寺澤さんも賛同した。

もともと登場人物が劇場内にいることは決めており、一旦、レイアウトのテスト用に岡田さんにイスだけ描いてもらい、そこに写真から切り抜いた人物を座席に配置し、それを基にある程度、岡田さんにお任せして進めたそうだ。意図を汲んだ岡田さんは少し上から魚眼的な構図で描き上げ、その仕上がりを寺澤さんは絶賛している。岡田さんについて寺澤さんは、上手い上に作業がとても柔軟だという。岡田さんのイラストにはタッチがいく通りかあり、打ち合わせでどういうタッチにするかやり取りしたそうだ。また使用媒体によって仕上がりの調整が必要なため、岡田さんからイラストのコントラストを変えたものを何種類かもらっている。イラストレーターへの発注の仕方について問われた寺澤さんはこう答えた。「絶対に押さえておきたいことは、嫌がられても伝えます」その上で信頼関係が成り立たなければならない。
寺澤さんが自らイラストを描いたものもある。それは男女12人の恋愛群像劇『サッドティー』(13)のメインビジュアル。頬杖をついた男性の写真の下にタイトルを挟んで5人の女性のイラストが描かれている。登場人物の写真をトレスする手法で描いたそうだ。このビジュアルの参考となったのは、寺澤さんが好きだという『地球は女で回っている』(97)のポスター。監督・主演のウディ・アレンと、彼をめぐる女性たちを描いたイラストが目を惹く。寺澤さんは『サッドティー』のビジュアルにキャッチーさとサブカルチャー感を加えるため、イラストにすることを決めたそうだ。

手書きによるタイトルロゴ
寺澤さんの手書きによるタイトル・ロゴのデザインも絶妙だ。今回取り上げた事例では、『佐々木、イン、マイマイン』、『アルプススタンドのはしの方』、『銀平町シネマブルース』が寺澤さんの手書きによるもの。

ロゴを手書きで作る場合、まずはパターンをたくさん書き、ぼんやりと浮かんでいるイメージ、その文字の形にどんどん近づけていくそうだ。例えば『アルプススタンドのはしの方』の場合、まずは「アルプス」の文字をたくさん書き、各々の良い部分をチェックして絞っていく。その上で「ア」の形は良い部分はどこで、なぜ良いのかを考える。それを念頭に置きながらさらに書く。文字組みのために3、4パターンを選んで、一文字、一文字、編集で組んでいく。そうすることによって、例えば「スタンド」という文字の場合は「ド」の縦棒の気持ちいいと感じる長さがわかってくる。それを踏まえてまた書く。再び編集で文字を組んで、文字サイズを調整し、それに合わせてさらに書く。そういった作業を何度も繰り返しつつ、細かな調整を加えながら仕上げていくようだ。
「アルプス」の「プ」の文字の「°」は閉じていない。寺澤さんはそのことについて「その当時、閉じないというのをよく目にしました。書き文字がすごく多かった時期。閉じないことで若さが出るんじゃないか? と思いました」と語った。『アルプススタンドのはしの方』は高校生たちの青春群像を描いた作品である。
コミュニケーションが生まれる距離感を考えること
「これは僕の考えですが、映画と宣伝ビジュアルの適切な距離がどこなのか、それを考える作業がビジュアル作りにおいて、基本の物差しだと思っています」
参加者からの質問「宣伝美術を映画本篇の内容にどこまで寄せるか」に対する寺澤さんの答えだ。ポスター等には映画そのものは映らないわけで、キャッチコピーが映画の売りを凝縮しているとすると、キャッチコピーと画の関係が大切だと語った。映画の内容に近づいて、ただ説明しているだけだと、受け手とのコミュニケーションは一瞬で終わってしまう。逆に離れすぎると伝わらないので、受け手に入口にすら入ってもらえない。距離の取り方は映画によっても異なる。デザイナーは都度、適切な距離を意識しながら、いろんな手法を使って、その映画の宣伝美術に相応しいデザインに仕上げていく。
「大事なのは、感じさせつつ、ある程度含みがあり、ビジュアルとお客さんとの間でコミュニケーションが発生する距離感だと思います」
寺澤さんが語ったこの言葉は、「映画宣伝美術の秘密」を解くカギのひとつだと思う。