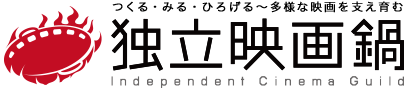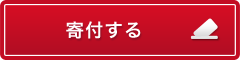【採録】第19回東京フィルメックス 連携企画「インディペンデント映画と公的支援~日本の映画行政について考える~」●Part 1: アジアの実情を知る

【日時】2018年11月18日(日)10:00開場 10:30開始(13:30終了)
【会場】ビジョンセンター東京有楽町 C・D合同ルーム
【ゲスト】モーリー・スリヤ[映画監督]
ドゥウィ・スジャンティ・ヌグラヘニ[映画監督]
【聞き手】市山尚三[映画プロデューサー/東京フィルメックス ディレクター]
【総合司会】土屋豊[映画監督/独立映画鍋 共同代表]

第19回東京フィルメックス連携企画は3部構成で、Part 1では「アジアの実情を知る」をテーマに、インドネシアからの映画監督をお招きし、インドネシアのインディペンデント映画の実情と、インドネシアの映画への公的支援について、お話をうかがいました。
Part 1: アジアの実情を知る
土屋:映画鍋では、これまで日本の映画行政、公的支援に関するイベントを何回かしてきていて、インディペンデント映画になぜ公的支援が必要なのか、映画業界以外の人たち、社会に向けて、納税者に向けて説明する言葉を自分たちで紡ぐことはできないか、を考えてきました。それを少しずつ進めるために、今回のようなイベントを積み上げたいと思っています。今回、インドネシアのお二人に、インドネシアのインディペンデントの状況をお話頂きます。

モーリー:こんにちは。モーリー・スリヤです。2007年から映画製作に入り、これまで3本の長編を作っています。
ドゥウィ:私はドキュメンタリー映画作家で、2002年から制作を始めています。ジョクジャカルタで国際映画祭の開催、また、インディペンデント映画に公的支援をする助成金の委員を4年間担当しています。
市山:インドネシアのお話の前に、 イスラエルのケースでは、独立した、日本で言う芸術文化振興基金みたいな映画に特化したイスラエル・フィルム・ファンドがあり、FILMeXでも紹介した『戦場でワルツを』や『レバノン』など、はたから見るとイスラエル政府には都合の悪そうな映画が、堂々と助成金をもらっています。イスラエルにも普通の娯楽映画はあるが、アーティスティックな作品は資金回収が出来ないような小さな公開となり、そこで共同制作を進めたりするのがファンドの仕事です。去年のサミュエル・マオズの『運命は踊る』という作品で、ベネチア映画祭でグランプリを獲得後に、文化大臣から「イスラエルの国の利益に反する作品にファンドが助成していいのか?」と発言し、大スキャンダルになったことがありました。でも公開はされて、サミュエルは「いい宣伝になった」と冗談交じりに話していました。
話を戻しますと、インドネシアのインディペンデント映画がどうなっているのか、モーリーが作っているようなアーティスティックで優れた作品がどのように作られているのか知りたいです。

モーリー:インドネシアの映画産業はアート系とメジャーの二つに分けられます。国の人口は2億5千万人で、全国に1,000スクリーンあり、スクリーン数は増えています。ほとんどの映画はローカルな観客に向けた作品で、文脈がわからない観客には意味が通じないほど地方性の強い映画が大半を占める一方で、作家主義の映画づくりをしている人たちがいて、こういった映画が世界の映画祭に呼ばれています。アート系の映画に関心を持つ観客は少しずつ増えています。インドネシアのおもしろいところは、映画配給が流動的で、誰でも手をあげれば公開できるオープンなマーケットであることです。
最近スクリーン数が増えて観客が増えているなか、映画に投資したいという声が海外のみならず、国内からも出ています。既存のシステムがないので、出資者は個人的な人間関係で参加作品を選んだりしています。どの作品が資金を得るのか、公開に至るのか、かなりランダムです。これではインドネシア映画産業にとって持続的な方法ではないので、今後制度を確立していく必要があります。国の公的支援制度はありませんし、私は地元の奇特な支援者や海外のファンドなどを頼りに、映画製作を進めてきました。
市山:昨年の作品賞を取った『マルリナの明日』は、どのように海外の助成金を取られたのでしょうか?

モーリー:フランスの共同プロデューサーがついたので、シネマ・デュ・モンドという(フランスの公的)映画基金にアクセス出来ましたけど、様々な世界の大スター監督たちと競合しなければならないので、決して楽に取れるわけではないです。インドネシアの監督にとって難しいのは、企画書を書くことです。英語、しかも上手く書かなければなりません。私は英語が第一言語ではありませんし、国外の人たちに助けられながら申請書を完成させ、応募せざるを得ません。
市山:補足ですが、シネマ・デュ・モンドの助成を受けられた諏訪さんと深田さんがいらっしゃるので、事情は良くご存知だと思います。1〜2本目は優遇されるんですが、3本目以降は、世界の巨匠たちと競わなければならないので、3作目は取るのは大変だと言われる中、彼女は見事に獲得されました。
モーリー:シネマ・デュ・モンドは脚本が審査の主体となる申請で、私の作った映画のように文化背景の文脈が言葉で記しにくい場合、どうやって説明すればいいのか、書けばいいのか。スンバという地域の常識は、映像になって見ればわかることでも、文字にしていかねばならないことが、結構大変でした。このようにして作られた映画を、逆にインドネシアで見せた場合、私が海外で教育を受けていることもあるし、客観的な描写を意識しているからか、西洋的な視点だと見なされ、地元での反応が良くないんです。「これは純粋な我々の文化ではない」と言われます。映画に対する公的支援があったとしても、おそらくこのような映画を支援しないのではないかと思います。ただし、海外で成功を収めると、これまた意見がひっくり返るのですが。
市山:今、国としてのファンドがなく地方に支援があるという話を伺いましたが、ドゥウィさんに、ジョクジャカルタのファンドの状況をお聞きします。

ドゥウィ:私が拠点にしてるジョクジャカルタは、インドネシアの特別州になっています。というのも、歴史的に王族が力を持っていた地域で、インドネシア政府から文化に対する特別な補助金を得ているのです。資金はかなりあり、文化一般に関する予算のうち2012年から映画に対する枠が設けられました。当時は、選考担当者の知り合いに助成金は流れ、いわゆる伝統文化を扱う映画に限った助成金でした。私は、そのような(伝統文化についての映画に限定した)資金の使い方はクローズドで正しくない、対象をもっと広げるべきであり、映画を作る人がテーマやジャンルを自由に選べる形にすべきだと、ジョグジャカルタのイファ・イスファンシャー監督やヨセフ・アンギィ・ヌン監督という有名監督たちと共に、提言しました。
その代わり、助成金を使って作られた作品は、インドネシアの法律に触れないものにします、と文化省に約束することにしました。特に、ポルノ的な表現の含まれているものは作らない、というようなことです。自己検閲をするのです。そうしたら、地方行政機関の方は、2015年から助成金のシステムをよりオープンにしました。私は助成作品の選定委員として関わってきましたが、(ここのところ)助成作品が、より豊かになってきているのが見てとれます。中には論議を呼ぶ作品もありましたが、それは処女性について取り上げたものでした。作品を通じて、どうして男性は結婚前の性的な関係が許されるのに、女性はそうでないのかということを、より広く社会の中で議論して欲しかったのです。
こういった内容の映画については、上映前に地方政府に説明に行きました。「多分、これは社会的に色々な反論を呼ぶだろうが、社会的に議論が広まることを意図した作品なのだ」と事前に話しました。実際、上映後に「どうしてインドネシア社会でタブーとされる事柄を取り上げる映画を作るのか?」という観客もいました。そういった人に対しては「あなたは作品で何を観たのですか?」と問い返しました。作品の部分部分を見るのでなくて、全体を見てください、と言いました。地方行政府は、インドネシア社会でタブーとされている事柄を描いた作品に助成したわけではありません。意図されたのは、インドネシア社会に存在するジェンダーの不平等について考えを巡らせて欲しい、という期待だったのです。

他に、インドネシアで作りにくいのは、例えば1965年の悲劇、「9月30日事件」に関する作品です。私たちはこうした作品でも、公的な助成金にアクセスできる制度を創りたいと思っています。その方法として、映画の制作者にちょっとだけ、自分で「検閲」してみては、と話をしています。例えば、話の内容はそのままであっても、描写をちょっとだけ変えることを提案します。65年の事件に関係した国軍の制服は現実のものに似ていても、エンブレムは現在のものと異なるものに変えるとかです。
その他にも、公的支援の制度改善の提案も行っています。例えば年度ごとに助成されるので、実質的には5ヶ月間で映画を作り上げなきゃいけない制限となります。そういった制限がよりゆるやかになることを、地方行政府に対して提案しています。ただ行政でそれを変えていくには議会で承認されなければいけないので、時間がかかります。
また、私たちは地元のキーパーソンと会って話をして関係を築いています。助成金システムを変えていくには、地方議会のキーパーソンが誰なのか、という情報を集めて会いに行く。あるいは、地方政府の文化局やジョクジャカルタ王宮関係者の中のキーパーソンに会いにいって関係を築きます。ジョクジャカルタ特別州の助成金を得て作られた作品が最近、インドネシア映画祭で賞を取って、ジョクジャカルタ特別州は映画の振興に貢献した地域として賞を与えられました。ジョクジャカルタ地方行政は映画に関する予算を増やし、私たちが求めたように使われなくなった映画館を再建することによって、インディペンデント映画を上映するための上映館を作っています。
さらに、地方行政の助成金で作られた映画が海外の国際映画祭に選ばれ、州知事が映画に対する公的資金の枠をもっと増やせと動きだしたこともありました。いまジョクジャカルタの映画助成は、短編映画に対するものだと1作品あたり15,000米ドルですが、その額を引き上げて、長編映画にも助成されるようにしたいと思ってやっています。ただ、地方議会を通さなきゃいけないので、多分2年ぐらいかかるだろうと思っています。
土屋:僕からですが、自主規制をしながら交渉しているそうですが、作家たちからその点が問題になったことはないですか?

ドゥウィ:私たちは、国にされるより自分で検閲する方がいいと話しています。フィルムメーカーたちは「自己検閲」について知っています。インドネシアには半ポルノグラフィ法がありますが、その法律に抵触しない限り、そのように創造的であっても良いということを。
________________________________________
モーリー・スリヤ Mouly SURYA[映画監督]
1980年生まれ。オーストラリアの大学でメディア芸術、文学、映画を学ぶ。監督デビュー作『フィクション。』(2008)に続く第2作『愛を語る時に、語らないこと』(13)はサンダンス、カルロヴィヴァリなど多くの国際映画祭に選ばれ、ロッテルダム映画祭でNETPAC賞受賞。第3作『殺人者マルリナ』(17)はカンヌ映画祭監督週間で上映後、世界の映画祭へ。第18回東京フィルメックスでは最優秀作品賞を受賞。本年東京フィルメックスの審査員。
ドゥウィ・スジャンティ・ヌグラヘニ Dwi Sujanti Nugraheni[映画監督]
ジョグジャカルタ出身。ガジャ・マダ大学で政治学を専攻。地元NGO、国際NGOなどで働いた後、映画製作を始める。2003年以降、ジョグジャカルタ・ドキュメンタリー映画祭の運営に携わる。2007年には米国ケンタッキー州のコミュニティ・メディアセンター、2009年にはニューヨーク市の映画配給会社ウィメン・メーク・ムービーズにインターンとして勤務。初長編『デノクとガレン』(2012)が山形国際ドキュメンタリー映画祭2013アジア千波万波で上映。
市山尚三 [映画プロデューサー/東京フィルメックス ディレクター]
【採録】山岡瑞子
【通訳】藤岡朝子・亀山恵理子・谷元浩之
【メインビジュアルデザイン】鈴木規子