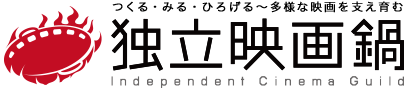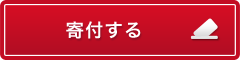【鍋講座 vol.35レポート】「インディペンデント映画の脚本ってなんだ?」
【開催】2017年9月6日(水)、於下北沢アレイホール
日本映画界の第一線で脚本家として活躍している3名をお招きし、参考作品を中心に「よい映画の脚本とはなにか?」をテーマとして、アプローチと方法論を伺い、とことん語りあった今回の鍋講座。来場者の皆さんで超満員の会場の中、熱気に包まれながらスタートしました。
脚本執筆をこれから目指す方、また、すでに脚本執筆を職業としている方も、ぜひ今回のレポートを読んでいただけたら、と思います。 (文責:上本聡)
【ゲスト・プロフィール】

高橋泉(写真右)
1973年生まれ。社会の暗部を照らすサスペンスなど商業映画からインディペンデントまで横断的に活躍している。主な作品『ある朝スウプは』(03)『ソラニン』(09)『100回泣くこと』(13)『凶悪』(13/共同脚本)『フジコ』(15)『ミュージアム』(16/共同脚本)『わにとかげぎす』(17)、公開待機作に『トリガール!』(17)『坂道のアポロン』(18)
向井康介(写真左)
1977年生まれ。山下敦弘監督作品の脚本を多く手がけ、ユーモアと何気ない感情の機微を描き出す。多な作品『リンダリンダリンダ』(05)『俺たちに明日はないッス』(08)『色即ぜねれいしょん』(08)『マイ・バック・ページ』(11)『もらとりあむタマ子』(13)『ピースオブケイク』(15)『聖の青春』(16)『愚行録』(17)
髙橋洋(写真中央)
1959年生まれ。90年代Jホラーを牽引し、単に怖がらせるどころかある濃厚な世界観を構築してしまう。『離婚・恐婚・連婚』で90年に脚本家デビュー。『リング』『リング2』(98、99 )、『リング0 バースデイ』(00 )『女優霊』(95 )、『インフェルノ蹂躙』(97 )、『復讐 運命の訪問者』『蛇の道』(96、98 )、『発狂する唇』『血を吸う宇宙』(99、01 )、『おろち』(08 ) 『予兆 散歩する侵略者』(17)、監督作『ソドムの市』(04)『狂気の海』(07)『恐怖』(09)『旧支配者のキャロル』(12 )監督最新作は来年春公開の『霊的ボリシェヴィキ』。
【司会】
舩橋淳
(映画作家・独立映画鍋会員)東京大学卒業後,ニューヨークで映画製作を学ぶ。処女作の16ミリ作品『echoes』(2001)アノネー国際映画祭で審査員特別賞・観客賞を受賞。『Big River』(2006)ベルリン、釜山等の映画祭でプレミア上映。アルツハイマー病に関するドキュメンタリーで米テリー賞を受賞(2005)。ドキュメンタリー「フタバから遠く離れて」(2012)ベルリン国際映画祭で上映、音楽担当の坂本龍一と登壇。劇映画『桜並木の満開の下に』(2013年)「フタバから遠く離れて 第二部」5作連続ベルリン国際映画祭正式招待。新作「LOVERS ON BORDERS」(映画史上初の葡日米共同制作)公開待機中。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
現在の日本映画界における脚本家の地位とは

まず最初に、司会の舩橋さんが挨拶し、現在の日本映画界における脚本家の地位について、以下のように語りました。
「日本映画の世界における脚本家は、1930年代から1950年代にかけての日本映画全盛期、また邦画各社のスタジオシステムが崩壊する直前の1960年代までは、きちんとした待遇と地位が確立されていました。もちろん、現在もプロの脚本家の方はたくさんいらっしゃるんですが、皆さんフリーの方が多いです。邦画メジャー5社(東映、東宝、松竹、日活、大映)に社員として雇用されていた頃に比べると、厳しいものがあります」
舩橋さん自身も、諸外国に比べて、日本では脚本家の地位が低いと感じています。脚本執筆にかかる時間、注がれるエネルギーに対する対価が、わが国では正当に支払われてないのが問題であると語りました。
続けて舩橋さんは、「たとえば韓国では、国を挙げて映画の脚本というものに力を入れています。脚本開発の時点での脚本家への報酬や、大学の映画学科で脚本を教えるために一線級の脚本家を迎え入れるなど、手厚いケアがなされています。一方日本では映画製作者が『脚本が出来たら持ってきて』というような状態で、脚本を書いている間は対価が支払われない。つまり、企画開発に使う時間とお金が無視されているのが常態化しています。わが国では脚本執筆に対する待遇がアメリカ、フランス、韓国などに比べて著しく低いです。なんとか日本の映画業界における脚本家の社会的地位を向上できないか、という思いを常々抱いています。脚本執筆が、これだけ大変で、面白くて、労力がかかることを知って欲しいと思い、そこで今回の鍋講座を企画しました」と語ってくれました。
ゲスト3人の紹介

続いて、舩橋さんは…。
「脚本の一番難しいところは、執筆時点では、誰が演じるのか、どこで撮影するのかが、あまり決まっていないです。脚本家はその段階で想像して、映画全編を頭で構築していくのが大変だということです。目利きでないといけないんです。脚本を書いていて、勝算があるとき、そうでないときなど…。そこで今回は、書いていく中で、これは(作品の大事な部分が)つかめたと思う瞬間、過程とは何なのかを検討したいです」と語り、ゲスト紹介へ。
まず、映画『凶悪』の予告編を上映後、高橋泉さんが挨拶し…。
高橋泉:これは白石和禰監督の作品で、4年前ですね。何をラストに持ってくるかがいちばん大変だったです。ただ「普通に記者が勝ちました」という話にはしないようにと思ったんで。…大変だったですね。
舩橋:僕も、これはどうやって原作を映画化するのかなと思っていました。てんでんバラバラな要素をどうまとめるのかなと。キネマ旬報や、日本アカデミー賞で、脚本が高い評価を受けましたね。
次に、映画『愚行録』『リンダ リンダ リンダ』の予告編上映後、向井康介さんを紹介。
舩橋:向井さんは山下敦弘監督と大阪芸術大学で『どんてん生活』でキャリアをスタートしたんですが、その当時、脚本と照明を担当されてたんですよね。
向井:あんまり僕以外にそういう人はいない、と思うんですが…。照明をやる人がいなかったんです(笑)。もともと好きだったんですね、そういうことが。撮影も、フィルムも、カメラも好きだったんです。そして…。30代半ば頃から他の監督とも作品ができるようになったり、いろんな興味が湧いてきました。NHKの連続ドラマなども手がけるようになりました。見てくれる方のターゲットが作品ごとに違うので、いろいろ考えて脚本を書いています。
舩橋:キャリアが広がってきたんですね。
そして、高橋洋さんが脚本を手がけたWOWOWのドラマ『予兆 散歩する侵略者』、来春公開予定の監督作品『霊的ボリシェヴィキ』の予告編を上映しました。
舩橋:『予兆 散歩する侵略者』、これはとてつもない作品です。セットの数などの制約もあるなかで、ものすごい作品です…。
高橋洋:そして『霊的ボリシェヴィキ』。これはタイトルがすごいんですが、このタイトルの由来は、日本オカルティストのドンのような武田崇元さんという方が、70年代に提唱した概念です。ボリシェヴィキは、ロシア革命でレーニンが率いた革命党派で。革命的前衛、その霊的な人たちという意味です(笑)。普通、マルクス主義者の集団と霊はまったくクロスしないんですが、これを組み合わせるのが武田さんのすごいところ。これを聞いた瞬間に、これをタイトルにして映画を撮ろうと。この言葉を知ったのはオウム事件の頃でした。その当時はじめて武田さんのことを知り…。僕の念願の企画でして、やっとインディペンデントで実現しました。
舩橋:『予兆 散歩する侵略者』。これは黒沢清監督の映画『散歩する侵略者』の、同じ監督によるスピンオフドラマ企画ですね。
高橋洋:劇団イキウメの原作があって、原作者の前川知大さんが小説も書かれています。映画のほうは舞台に忠実に作っています。いっぽう、スピンオフドラマを撮る、という話があったんです。その直前に、黒沢清さんと、彼の監督作『クリーピー 偽りの隣人』について対談する機会がありました。その際ピンと来るものがあったらしく、「『散歩する侵略者』をスピンオフでやるんですが、侵略恐怖ものにしたいので、高橋さん、同じ世界観をベースに脚本を書いてくれないか」と。それで、すぐ引き受けました。
舩橋:僕は映画版とドラマ版、その両方を拝見したのですが…。予算はドラマ版が圧倒的にかかっていない。だけど、しびれました、こっち(ドラマのほう)に。病院とアパートしか、舞台として使っていないけど、こんなキレッキレの作品になるんですね。まったく無駄がない作品で、怖がらせるところは怖がらせ、引っぱるところは引っぱって…。なぜ高橋洋さんの、この二つの作品の予告編を上映したかというと、今回のテーマでもあるんですが、皆さん、商業映画と、インディペンデント映画を往復するようにしながら作品をたくさん創られているんです。その三人を、今回は、ゲストとしてお招きしました。今日は低予算で作る作品と大きなバジェットの商業作品、その両方についてお聞きしたいと思っております。今回は事前に、それぞれの方と打ち合わせでお話ししたんですが、皆さんバックボーンが素晴らしかったです。そして打ち合わせの過程で、キーワードを見つけました。この、いくつかのキーワードを意識して聞いていただけると、この講座が終わった後で、これが串刺しのように、皆さんの中でつながるのではないと思います。まず1つ目は「作品の核」。その映画で、何を面白がるか、ということです。2つ目は「人物の奥行き」。それぞれの方がそれぞれのやり方で発展させたり、深めたりしています。3つ目は「映像による語りの工夫」。これも、それぞれの方が独自のやり方で発展させたり深めたりしています。そこに注目してもらいたいですね。
高橋泉さん・ドラマ『フジコ』について

各ゲストの紹介の後は、高橋泉さんが脚本を手がけたドラマ『フジコ』について、予告編や脚本のスライドの上映を交えて語っていただきました。
舩橋:まず、これ面白いな、と原作小説(真梨幸子著『殺人者フジコの衝動』)で思えたところは?
高橋泉:原作はぶっちゃけ、気持ち悪いですね。いわゆる「イヤミス」(読んでイヤな気持ちになるミステリー)といわれる、ベタベタドロドロした内容のものです。この小説は「主人公に感情移入できない」と言われていたんです。ガンガン人を殺しているので。ただ、僕は原作を読んだときに、フィクションだからというのもあるかもしれないんですが、主人公をどこかチャーミングだなと思ったんです。それでこの人を描いてみたいな、と思った。
舩橋:ドラマと原作小説では構成が変わっています。物語の要約を行っていく中で変えたんですか。
高橋泉:小説は「フジコが処刑され死んだ後、娘に手紙が送られてくる」という構成です。しかしドラマで「ドラマが始まった時点で、主人公が死んでいていいのか?」と思い、プロデューサーに提案し「生きているフジコに娘が面会に来る」という構成にした。主人公が過去軸にしか出てこない、というのは、作品としてありえないです。僕の提案を、プロデューサーは喜んでくれて「面白い」と。
舩橋:極悪非道な殺人鬼の主人公(尾野真千子さん演)に、感情移入して欲しいとか、かわいく思えるようになってほしいとか、そういう感じですか。
高橋泉:「彼女を、作品の創り手くらいは愛してやろう」という感じですね。ツイッターでドラマの感想をエゴサーチすると「感情移入はできないけど、泣いてしまった」という感想も多かったので、僕らとしては「これだけはこのドラマでやりたい」ということは伝わったかな…と思います。
舩橋:第1話の構成はどんな感じですか。
高橋泉:まず最初に、ある編集者に、手紙が送られてきてフジコの半生を語り継ぐんですが、実は彼女は、現在は大人になっていて、その少女時代が描かれます。事前には「そこからドラマが始まっていいのか」と言う議論もあったんですが、ドラマなので見やすく作ったほうがいいのかなと思いましたので、そこから始めました。
舩橋:今日は、その脚本を持ってきてもらったので、スライドで上映しています。
高橋泉:フジコという人間は、殺人鬼で、同時に、過去に親から虐待を受けていたり、美への追求が激しかったり、といろいろな要素を持ったキャラクターです。フジコにはジャーナリストになっている、美智子という娘がいて、この美智子がフジコのもとに面会にやって来ます。娘だということは、この時点では、まだ伏せられているんです。僕は最初にキャラクターをがっちり決めて書く、というよりは脚本を書きながらセリフをしゃべらせつつ、ふくらませていくんです。フジコは、いろんな要素がありすぎて何をやらせたらいいのかわからなくなりかけたり、今度は、物語はこうして進んでいくから、と製作者に言われるとすごく縮こまって書いてしまったりとか、なかなか主人公の全体像ができあがらず…。実は、脚本を頼んできたプロデューサーも、最初すごく困っていました。そのときに、面会に来た人物にいい顔をしようとしたりとか、少女のようでもあったり、美を追求したり、かわいいところもあり、と彼女のさまざまな面が一気に顔を出すシーンがあり…。フジコってすごくバラバラなんですよ。口調や、話す内容が。そのときに、この主人公は、バラバラでもいいんだ、ということがつかめたシーンですね。そのシーンで「あなたは虐待した」みたいとことをフジコが言われたときに「私、顔をたたいてない。絶対に顔はたたかない。そういうことは書かないでください」みたいなことを言ったりとか。「女は体型を気にしてデザートなんて食べなくなるのよ。食べるときは罪悪感がある」「表紙の写真は自分が二十歳くらいの美の絶頂期のときの写真にしてくれ」と言い出したり。フジコは思ったことをその場でしゃべっちゃっていいんだ、ということが分かったシーンでしたね。
舩橋:半分、多重人格みたいな感じで突き進んでいいんだと。
高橋泉:多重人格とは違うんです。むしろ彼女を多重人格として描くほうが簡単なんですけど。バラバラでも「これがフジコです」といえる何か、がないと…。
舩橋:ハコ書き(シーンのならびと各シーンの簡単な内容を書く作業)をはどうされてますか。
高橋泉:僕は頭の中で大体書いていくので…。いや、でも書いたかな?書いた中で、物語の進行の中では、実はフジコと言うキャラクターはつかめなかったです。僕は勝手に書いていくんです。プロデューサーは面白がってくれたんですけど。次に、フジコの娘が二人いるんですけど、フジコに虐待されていて、またフジコの連れあいもネグレクトをしている。早い段階で、この娘二人の絆をしっかり描いておかないといけないんです。また、ピンクのリップクリームというのが、物語の中で真犯人を見つけるときのキーになる。それをただ「鏡台などに置いてある」と書いても、つまらない。そこで、フジコの娘二人はご飯を食べさせてもらえていないので、彼女らがリップクリームを「これ、食べられるんじゃないの」と言うシーンにしてみたら面白いのでは、と思いました。
舩橋:書いていくうちにアイデアがポンポン出てくるんですね。
高橋泉:原作には、このシーンはなかったですね。
舩橋:原作者の方には、どの段階で見せていくんですか。
高橋泉:第1話を書いた時点で一回見せてます。でも、真梨さんは「脚本は読まなくていいです」みたいな感じでしたので、読んでないかも。でも仕上がりには満足してくれたのでよかったです。
舩橋:最初はフジコが監獄に入っていて、ジャーナリストになっている娘の美智子が訪ねてくる。そして話を聞き書きして、書き起こしていく。現代の時制でフジコと美智子が語り、過去がフラッシュバックして展開する、という構成ですね。フジコは殺人鬼で、明らかにおかしく描かれています。そしてフジコの交際相手の男もDVで、フジコの娘たちをボコボコにしてしまいます。しかし、なぜかそれをフジコが助ける。
高橋泉:この主人公を、ちゃんとした母親にしてはいけない、と思っていて…。第6話のラストでようやく、母親と娘の、はじめての親子喧嘩をするんです。しかし、そこまでは彼女は絶対「母親」になってはいけない、というのがありました。あくまでも、それを見せないようにしていくという脚本を意識しました。
舩橋:次第に、フジコの違う側面が出てくるんだけれども…。彼女は明らかにおかしいんだけど、時々、気まぐれに自分の娘を救ったりする側面もある。今、スライドに出ている脚本の赤く引いている箇所は?
高橋泉:血のついた千円札が数枚出て来るんです。これは人を殺して手に入れた千円札で、これが(ブラックな意味で)すごい笑えるんです。だって、娘の給食費をどうにかしようと、最初昔つとめてたスナックに行くんですけど、そこで、あんたみたいな子汚い女を雇えないと言われ、その足で美容院へ行ったりあちこち行きながら、全員殺しちゃう。そして、近所で自分のことを「整形狂い」と言っていた人を殺して手に入れた三千円なんです。金は血塗れていて「やっぱりこいつはおかしいや」と見せなきゃいけない。書いていてすごく難しかった。
舩橋:僕は全話見たんですが、最初は鬼のようなフジコが、時々断片的に奇怪な行動を取るんですね。子供に暴力をふるっておいて、給食費ちょうだいと言われたら絶対にあげない。その代わり化粧品は自分にバンバン買う。だから、ラストで給食費を出すのが異様に映りますね。この虐殺はここでは出てこなくて、後々描かれるということですか。
高橋泉:そうですね。
舩橋:それは構造上、作っていくのは大変じゃないですか。
高橋泉:まあ大変でしたね。でもそこは、脚本はチーム戦だと僕は思っているからプロデューサーに頼っちゃう。「僕は自分のやれることはやるから力を貸してください」と。
舩橋:では、ハコ書きを考えながら「ここはまだ出さないで、ここにこれをまぶして」などしながら、全6話分にプロデューサーとまとめていくんですね。ハコで全体の設計図を創りますが「どこでこれはいける、脚本に書こう」となりますか。
高橋泉:いちばん盛り上がるところが見つかったら、そこでゴールというか、僕の中では作品をつかめます。全6話全部ひっくるめて考えて「これはいける」と思ったんで。
舩橋:では、長い三時間強の映画だと思って。
高橋泉:はい。
舩橋:この第1話での、語りの工夫でびっくりしたのが、フジコとずっと相対していた「私はあなたについて書き立てますよ」というジャーナリストが、実はフジコの娘だったという。フジコに暴力を振るわれていた実の娘、姉妹の妹のほうだった!なぜ「お母さん」と呼ばないのか、という理由がだんだん分かってくる。ジャーナリストとの会話かと思っていたら、この話のラストで娘と言うことが分かって、それまで我々が見ていた景色が、まったく違ったものになってしまうという展開になります。「これは映像で語る上で非常に面白い工夫だな」と思いました。谷村美月さん演じる美智子を、視聴者がジャーナリストとして認識しているのがひっくり返る。これは原作にある展開ですか。
高橋泉:ちょっと覚えていないですね。
舩橋:すごいどんでん返し。「やっぱり第1話だからいこう」みたいなことは?
高橋泉:そうですね。これは最終話までひっぱっていく案もあったんですが、この作品でやりたいのはサスペンスではなく「何代かの負の螺旋が続いている家族のドラマ」だとなったときに、サスペンスを引っぱるのではなく、第1話で明かしていこうとなったんです。原作は『殺人鬼フジコの衝動』ですが、こちらは『フジコ』というタイトル。殺人鬼を描きたいわけでなく、衝動を描きたいわけでもない。「フジコという、女を描こう」と製作チーム全体で決まったときにそうなりました。
舩橋:商業映画の脚本と、ご自身の監督作品ではスタンスの違いは、あるのでしょうか。
高橋泉:ぜんぜん違います。作品を見る人たちの層がまず違う、というのがあります。商業作品の脚本は、まず女子高生など、若い人たちを想定して考えます。対して自主映画では、自分がまず客席にいることを想定します。その世界の中で作っているので、誰に届こうが届くまいがかまわないというか…。商業作品において作品のニーズを一般に広げていくことは、濃度を薄めていくことでもあります。自分のいちばんやりたいことを、自主映画作品ではやっています。濃度を薄めていくことばっかりだと自分というものがフワフワしていく感じがする。「自分とは何か」を考えながら40歳くらいのオジさんが自主映画を撮ってるわけです(笑)。自主映画を創っていると、自分が面白いと感じるものも変わっていくので、商業とインディペンデント、両方やっていて面白いなと思います。
舩橋:「監督と脚本家がこういう関係になると面白い作品が生まれるよね」というのはありますか。
高橋泉:チーム戦になったときですね。なかには、チームのメンバーとして(脚本に)参加してくれない監督もいるので…。監督がキング・オブ・キングで、僕らは監督の脳内イメージを書き起こしているだけ、みたいなときもなくはないので。それよりは、ダメだしでもガンガン言ってもらって、僕もガンガンアイデア出して、膝突き合わせて創作していくことになると、面白いなと思いますけどね。
向井康介さん・映画『もらとりあむタマ子』について

次は、向井康介さんが脚本を手がけた映画『もらとりあむタマ子』について、予告編や脚本のスライドの上映を交えて語っていただきました。
舩橋:なぜこの作品を、今回の鍋講座で選んでくださったんですか。
向井:大阪芸大での卒業制作、山下敦広監督との映画『どんてん生活』で、一応脚本家と言われるようになったんですが…。そのころの創り方と、『もらとりあむタマ子』執筆当時の2013年の創り方は…。商業作品もいろいろやった後で、ひさびさに自主映画時代と同じような感覚でやれた映画、やった映画ですね。そこが印象的だったので選びました。
舩橋:山下監督の『リンダリンダリンダ』の後、他の監督さんとやるようになったりされて…。10年ほど経って、もう一度山下監督とタッグを組まれたんですね。
向井:「なんでこんな感覚になったのかな」って今回の企画のこともあって、自分で振り返ったんですけど。山下君と俺が一緒にやるときって、普通、映画の題材は、原作があったり実在の事件などから題材を選ぶと思うんですが…。山下君でやるときって、「人」から入るんですよね。「あの人が面白い」とか。「あの人に出て欲しい」とか。「あの顔」が面白い、「あんな面白いことがあった」とか、『どんてん生活』や『ばかのハコ船』のときは、そんな感じで映画創ってたんですよ。それが、この作品のときはプロデューサーから「ある番組と番組の間に、10分くらいで入れられるような短編映画を。前田敦子を使って何かできないか」と言われたときに、あ、じゃ「この人」で何かを創っていこうと。今回これは「前田敦子」から、入ってるんですよね。そこはひさびさというか。
舩橋:では前田さんの存在が、画面でこんな感じだと面白いんじゃないかと。
向井:前田敦子を使ってそれまでにない顔を出す、それにはどういうシチュエーションや境遇とかがいいのか、考えました。彼女にもやる気を出して欲しいし。
舩橋:この作品では前田さん演じるたま子は、劇中マンガ読んで、コンビニの菓子食って、そのへん散らかして…。いつのまにか寝ているという不細工な描写が続くんですけど。あれはアイドルである前田さんが受け入れるまで、説得に時間がかかる気がするんですが…。
向井:いや、ああいうのは、彼女はぜんぜん気にしないです。何でもやってくれる人です。むしろ、こっちの趣味が出せたかもしれないですね。
舩橋:とってもミニマムなお話ですよね。甲府のスポーツ店の親父と、引きこもりのモラトリアムの娘という、ふたり中心の。
向井:僕、個人的にはいろいろ伏線をはりめぐらせたミステリーとか読んだり、映画で観たりするのは好きなんですけど。いざ、やろうかとなったとき、山下君って「人」にしか興味がなくて。伏線とか提案しても「そこに何の意味があるのか」って言われると「ないけど気持ちいいじゃん」て(笑)。で、「人」に寄っていくと、設定がどんどんミニマムになっていくんですよ。シチュエーションも…。登場人物も3人くらいとか。そのシチュエーションでどう展開するのか、とか。『リアリズムの宿』まではそんな感じでシチュエーションとシチュエーションを串刺しにしていくような、そんな感じの映画がほとんどだったんです。話を戻すと、最初10分でできる企画ということだったんで、最初、秋、冬、春、夏の4エピソードで各10分ずつ撮ろうとなり…。最初、秋、春、と撮ったんです。そしたらプロデューサーが「これ、もうちょっと長くできないか。全体で60分以上になったら映画として公開できるかもしれないから」と。あわてて夏のエピソードをこしらえてくっつけたんですよね。だから、構成がいびつなんです。
舩橋:夏のパートが長いですよね。
向井:プロデューサーには「最初から言ってくれよ」って言ったんですよ。そしたら秋と冬は、何も話がない。でもまさにそれがやりたかったんです。要はどういう風に日常を描くのか、日常の中の非日常をどうするのか。そこをどう汲み取っていくのがの違いが、作家性の違いになるような気がするんです。山下君が監督としてやるのは「どこまで何もやらないで、ドラマを作らないで、どこまでドラマをやれるのか」なんです。
舩橋:ほんとにこの台本、最初のころはモラトリアムしている描写が…。たま子が、飯食ったり、テレビ見たりで。
向井:選んだシーンは、主人公のたま子が、都会で就職活動に失敗して実家のスポーツ用品店に引きこもっている。そこには父親しかいなくて、父親の仕事を手伝うでもなくだらだら生きている。ちょうどここは大晦日のシーンで、東京から姉一家が帰ってくる。紅白を見てゆく年くる年を見て、寝ちゃったたま子が目覚めると、父もテレビを見ていて…。そこのやりとりのシーンです。ここで、はじめて父と娘以外の人間が登場する。それもどこまで遠回りして感じさせるか、という。要は日常を覗き見している感覚に、お客さんになってほしいと思って…。それで、そういう風なセリフで脚本を書きました。
舩橋:ドキュメンタリーで、偶然生活の一部が映ったみたいな。
向井:なんとなく家族の話してるのはわかるんだけど、全部はわからない、でもわからせたい、みたいな。
舩橋:会話だと「母さんは離婚して遠くにいるんだな」くらいな感じですよね。
向井:そういう感じをわからせたい。後半は、部分によっては脚本どおり山下は撮らなかったですけどね。そこがすごく面白かったです。監督に負けたなと…。また課題としてあったのは、夏のパートを創らないといけない。父親に再婚相手ができるかもしれない、という部分ですね。すると、たま子の居場所がなくなる。それで父親のお見合い相手を偵察したりする。めぐりめぐってアクセサリー教室を経営している、お見合い相手(富田靖子さん演)に会いに行った、というシーンです。
舩橋:父と二人暮らしのたま子の、停滞した世界が変わろうとしているわけですね。
向井:たま子が彼女に結婚をやめさせたいから、父親のことを「最低なやつ、結婚にふさわしくないやつですよ」と告げに行く。しかし言えば言うほどたま子の父への愛情、思いがあふれてしまう。それを彼女も理解して「再婚しない理由がわかった」と身を引いていく、というシーンです。脚本は、作品全編で物語の流れ、序破急があります。しかし、ワンシーンのなかでもそれがあるんです。これはその典型的な序破急の3幕シーンかな、と思います。「ここはとにかくお見合い相手を偵察してやるぞ」とたま子が行動し、相手に身元がばれるまでが1幕の序。たま子が自己紹介から父のことをさんざん悪く相手に話して「まあでも一番だめなのは『私にこの家出てけ』って言えないことですよ」までは2幕の破。そしてここから3幕の急、が始まります。お見合い相手は、察して自ら身を引くが、逆にたま子は自分の中の罪悪感に気付く。父と相手を引き裂こうとしている自分に気付き、逆にフォローするような、会話のうねりが見えたとき、これは「なんとかなるかな」と。秋冬春夏を通じて「ここでしっかりした作品になるかもしれない」と、脚本を書いていて見えたのが、このシーンです。
舩橋:親子の関係が見えて、はからずも身を引こうとなってしまった彼女に、たま子がとまどい「私は見合いを邪魔しようと思ってなかった」と気付き自分に驚く…。
向井:次のシーンは、お盆で、東京から帰ってきた同級生と遭遇したというシーン。たま子は昔から一人でふらふらしていたので、その同級生は余り仲良くない相手です。でも、その前のシーンを受けて「そのまま流れで行ったほうがいいな」と、ここはぱっと思いついて、そのまま書いていったんです。その同級生がなぜか泣いている。そして、彼女にたま子は手を振る。
舩橋:主人公が変化する、その予兆を同級生を使って描いたと。
向井:そうですね。これが映画的手法かどうかはわからないんですが。いわゆる商業作品では、こういうことはやってないんですよ。この作品は、わりとインディペンデントで「好きなことやってください」ということなので、自分が「見たい」と思うものを書いたのを、山下君もやってくれて…。山下君がロケハン先から「カメラマンが『何で同級生は泣いてるんだ』って聞いてくるんだけど、何で泣いてんだよ」と。僕は「なんか泣いてんだよね」で押し切りました。結果、すごくいいシーンになったんですよね。よかったなっていう(笑)。
舩橋:ミニマムな物語の起伏の中で、たま子が成長、独り立ちしていくという話ですね。最後、父も主人公に「家を出て行きなさい」と言う。
向井:「いつ子供が親離れしていくか」っていうこと、逆に「親が子離れするところ」が夏のパートで見つかったんですよね。それを作品のテーマとして、落とし込んでいった。
舩橋:実はこの作品の展開、小津安二郎監督の『晩春』と同じなんですよね。
向井:よく言われるんですよね。で、山下君に行ったら『晩春』を、実は観てなかったという。(笑)
舩橋:『晩春』の原節子と、前田敦子。隔世の感がありますね。
高橋洋さん・映画『リング』について
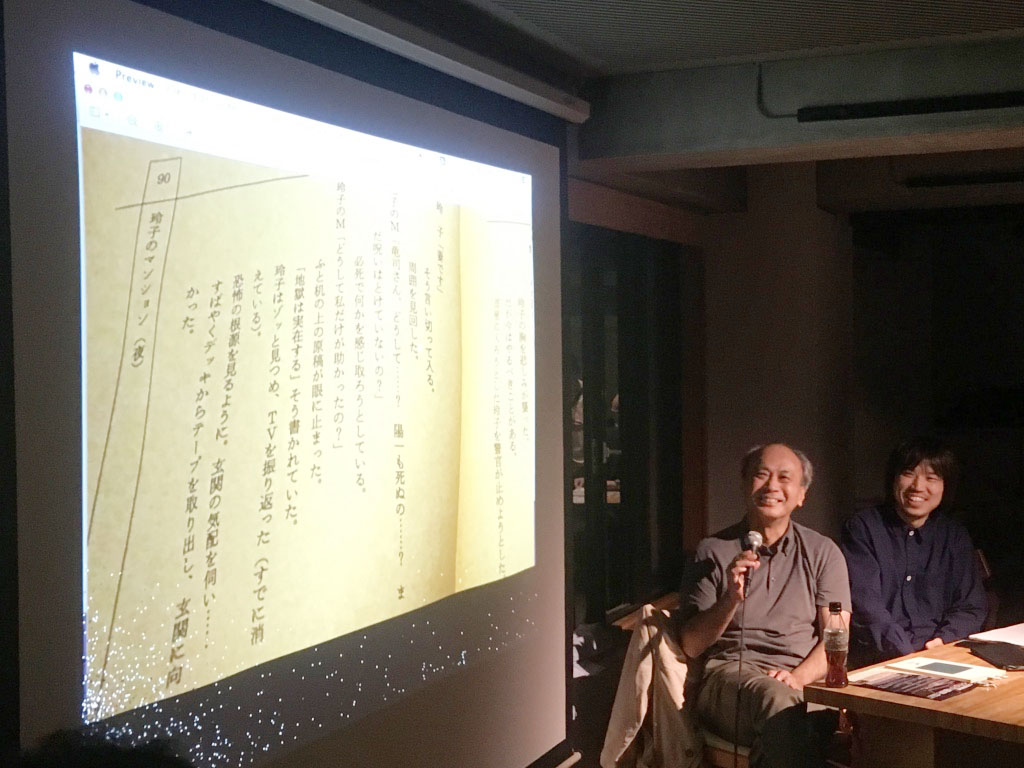
最後は、高橋洋さんが脚本を手がけた伝説の映画『リング』について、予告編や脚本のスライドの上映、ご持参いただいたノートなどを交えて語っていただきました。
高橋洋:この作品の成立の経緯は、その前に僕が脚本を書いた中田秀夫監督の作品『女優霊』を原作者の鈴木光司さんが観てくれていて、推薦してくれました。それで決まったんです。角川書店から原作が出てたんですが、原作者みずからが言うと映画の脚本と監督が決まる、という(笑)。鈴木さんは「『女優霊』テイストでお願いします」という話で「原作がこうだから」という話は一切言わなくて、完全にぼくらを信じてお任せしてくれた。それがほんとにありがたかったです。
舩橋:女子高生たちの奇怪な死の真相を追っていた主人公が、女子高生の間で噂になっていた「見た者を一週間で呪い殺す、呪いのビデオ」の存在を知る。そのビデオを主人公(松嶋菜々子さん演)は見てしまう。主人公の別れた夫は、協力してその謎を追ううちに超能力者の悲しい悲劇にたどり着く…。それが、あの「貞子」というキャラクターです。映画の脚本として執筆する際、原作をどう変えていったのかを、教えてください。
高橋洋:いくつか難しいポイントがあって…。「呪いのビデオ」は原作にも出ていて、この原作だと、「呪いのビデオ」は映像が終わった後に、ビデオに字幕で、呪いについての効能書きが出るんです。「それを映像でやるのは絶対にまずい」と。最後にビデオ画面に字幕で効能書きが出てしまうと、そこまでどんなにがんばって映像を創っても、そこでリアリティが崩壊するので。しかし作品のルール「呪いのビデオの死のルール」は、早めに示さねばならない…。そこで、はたと考え込んだんですが。では「最初から、女子高生の間の都市伝説になっていればいいんだ」と気付きました。そこで「これでこの作品は勝負できる!」とガーッと脚本を書き始めた。ノートにアイデアメモみたいなものは書いて、あとはワープロで打ちましたね。プロット、ハコ書きはプロデューサーとの打ち合わせ用、いわゆる提出用なので…。自分としては、ノートにいろんなことを書き散らしているときが、いちばんアイデアが出てきているときですね。おもにジョナサンとかで書いてます(笑)。
(ここで持参してきたノートとメモを掲げて)
「決定稿が9月8日」とあり「4月2日 中田さん戻り」と書いています。この頃から執筆作業を始めたんです。それで9月には決定稿が出来上がっていたんです。ノートのいちばん最初のページに、アイデアの最初の段階で「主役は女性で、TV局の取材ディレクター」とすでに書いてある。「子供がいて夫と離婚している」。ここで、もう原作を変えてます。
舩橋:原作は、男性の新聞記者が主人公。もう一人、男性のオカルト研究者で「彼に聞けばなんでも知ってる」というキャラクターがいたんですが、それが真田広之さん演じる、主人公の元夫に代わりました。彼には実は霊能力があって…。そのキャラクター変更によって、語りの経済性というか、話がどんどん進むようになっている。
高橋洋:ノートに書いてますね。「一種の霊能者でゴーストハンター」として。まだ、主人公の元夫という設定ではない。
舩橋:この作品では「貞子」は一回しか出てこない。いわゆるホラー映画では、ジャブと言うか、最初に幽霊が出てきて一回怖がらせてから、中盤でもう一回出て、最後にいちばん大きいのが、と言うような感じかと思いますが。この『リング』というのは出てくるのが1回だけなんですよね。問題にならなかったんですか。
高橋洋:そもそも、みんな観る前は原作の貞子をイメージしているので映画の中で、ああいう貞子が出てくるとは、誰も思っていないです。だから何回出すというのはないけど…。怖いシーン自体は出さないといけない。企画会議で言われたのは「呪いのビデオ」をペンションで見て、後に死ぬ人がたくさん出てくるんですが…。原作だと、この「死んで行く人たち」が次々と描写されている。製作チームの中では「これをやらないとだめだ。なぜならばお客さんにとっていちばん怖いのは死だ。死を描かないとダメなんだ」という意見が出ました。自分はそれに対して「それは常識的な発想に過ぎない。あなたは死が怖いというが、それは映像にしたら、餅がのどにつっかえて死ぬようなものしか撮れないよ。それで果たして、本当に怖いんですか」と。人が死ぬところは、悲惨だけど、ある意味ではこっけいに見えるというか…。「死ぬのは一番怖いことだ、という常識を超えて死よりも怖いものを描かないとダメなんだ」とその場で言いました。それがこの作品の「貞子」で、それが通った。そこで、この作品の基本線がはっきりしたんです。
舩橋:死より怖いもの=貞子は、作品中でいろいろ積み上がっていって、最後に出る、と。脚本のファーストシーンのあと、次のシーンでは女子高生たちが「呪いのビデオ」の噂をしていますね。
高橋洋:そうですね。「見たら一週間で死ぬ」のルールをここで提示しようと。ここは原作にはないシーンです。
舩橋:原作では、ひとつひとつの死の謎を解明していくのですが、それだとまどろっこしい。そこでドンドン勝手に人が死んでいく。その前に「これが映画のルールです」と宣言する。その次から人が死んでいるところなどが出てきたり、事件が起きてたりという…。その速さは、重要ですか。
高橋洋:そうですね。段取りを見せてもしょうがない。段取りより、ホラーの場合は特に余白、フレームの外にあるものを、想像させるほうが大事なんです。ですから死体も、死ぬ瞬間でなく「事後」ですよね。死ぬ瞬間を見せたのは、元夫だけでした。
舩橋:中田監督と、衝突などはありましたか。
高橋洋:いやもう『女優霊』のときからお互い首を絞めあいながら、ものすごいバトルを(笑)。それはもう、懐かしい。あのくらい本気で罵倒しあいながら映画創ったっていうのは…。それくらいやんなきゃダメなんだって思いますよね、本当。覚えてるのは、その前の『女優霊』で中田監督が幽霊の顔を出したんです。僕は「幽霊の顔を出すな」って言ってるのに出しちゃって。それで「今度こそ、絶対幽霊の顔出すな」って言いました。そしたら中田監督は「キャスティングに口を出さないください」など、色々あったんです。ある日僕が「TVのブラウン管から貞子が出てくる」というのを思いついて。でも中田さんはマジメな人だから「それはない」って言うかもしれないなと思って…。それで中田さんに電話したら、「面白いですね」と。これで「あ、いける」と思ったんです。
舩橋:「監督が面白がらないと、書くべきではない」って言うのはありますか。
高橋洋:そうですね。ただ書いたものをなぞるだけになるのは、お互いにとって良くないので、それは意味がないですね。
舩橋:『リング』で監督とぶつかったことはありましたか。
高橋洋:「貞子の目玉を見せたい」と中田さんが言い出した。そのときは大喧嘩になりました。「女優霊のときにあんだけ顔見せたらダメだって言っただろ。また目玉見せるのか、ダメって言ってるだろ!」って大喧嘩(笑)。でも結果を見たら中田さんが正しかった。そういって、もめる中で選び取ったもの、そこには何か、意味があるんですよね。
舩橋:それはなぜ、喧嘩になったんですか。
高橋洋:いや、人間の目玉を撮ったら人間の目玉にしか見えないですよ。それは作り物の怪物の目玉も同じで、作り物の目玉を撮ったらそういう目玉にしか見えないからです。目玉って難しい。「中田さんは、おそらく普通に撮ってしまうだろう。だからダメだ」ってもめたんです。それで…。有名な話ですけど、中田さんは助監督に命じて、眼医者行かせて麻酔打って彼のまつ毛を全部抜かせて「人間の目じゃないもの」にしてしまって、撮った。それだけ中田さんもプレッシャー受けたから…。意地でも「あの目玉を、人間の目玉じゃないものにする」って撮ったんです。
舩橋:命を賭けて目を撮ってますね。
高橋洋:そうやって追いつめあいながら、どっちでもないものが生まれてくるんです。パワーのある表現が。
舩橋:台本の最後のほうで、ご紹介したい部分があるんですが。最後に真田広之さん演じる主人公の元夫が呪い殺されるシーンの後のシーンがあります。これは、カットされたシーンです。
高橋洋:カットというか…。主人公が駆けつけてきて「呪いのビデオ」があるのを、持ち帰るシーンはあります。主人公の元夫が死ぬ直前に、ある原稿を書いてるんですが、テレビから貞子が現れる直前に、彼の手が勝手に動いて字を書きはじめる。その原稿に最後に、彼はなんと書き付けていたのか…、と言うシーンです。「地獄は実在する」と僕は書いてるんです(笑)。結果「これはよくわからないからやめよう」となりました(笑)。くやしかったけど、それはわかるな、と。メジャーな映画とインディペンデントな映画の違いはこういうところに突っ込むか、突っ込まないかだと思うんです。ですが、僕の中でコアなものはこの「地獄は実在する」なんですよ。
舩橋:なるほど。
高橋洋:このテーマを常にやろうとしてるんです。「メジャーでは無理」と言われたのであの手この手でやろうとしてるんです。さっきの向井さんの「泣いているのに理由がいるか、いらないか」と近いですね。あ、一緒にしちゃだめか(笑)。
舩橋:「リング」を原作、脚本、映画と読み、観ると…。恵まれない貞子の悲劇の物語にもなっていますね。単なる恐怖表現の作品じゃなくて、貞子の人物像が徐々に理解しながら、その悲しい人生に同情してしまう。最後に主人公が貞子を抱きしめるので泣けてしまうというか。いわゆる子供騙しの怖がらせホラーではなく、痛切な悲劇の終焉として呪いのビデオから貞子が出現すると、この怨霊は絶対的に強いぞ、やられる!となる。言ってみれば最後の最後に出てくるのは、脚本構造上の意味があると思うんです。
高橋洋:僕は『東海道四谷怪談』を常に意識しています。なぜ、あの作品に登場する「お岩」があんなに怖いかといえば、お客さんたちが彼女に対して罪悪感を覚えるからです。つまり、この人が死んだらいけない、ヤバイと皆が思う。しかし、彼女は死んでしまう…。貞子も超能力者であるがゆえに、いわれのない迫害を受けて死んだ人間です。そのドラマを与えたがゆえに、貞子に、ヤバイな、と皆が思うんでしょうね。
おわりに
約2時間にわたった、今回の鍋講座。今回のレポートでは、できるだけ現場の模様を皆さんにお伝えしようと思い、会話のやり取りの詳細までを記載しました。3人のゲストと舩橋さん、それぞれの方たちが自らの信念、哲学、人生観と常に向き合っていること…。そして、それを作品として昇華するため日々探求し続けている姿勢に、強く感銘を受けました。
私自身も脚本を手がけておりますが、作品そのものへの関わり方について、テーマのつかみ方について、改めて学ぶところ、また得るものが多かった今回の鍋講座でした。
(文責・上本聡)