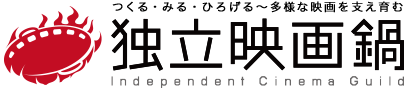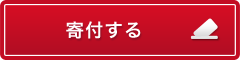【レポート:鍋講座Vol. 33】インディペンデント映画と映画祭〜TIFF&FILMeX〜

【ゲスト】
市山尚三:1963年生まれ。㈱オフィス北野に在籍。主なプロデュース作品に竹中直人監督作品『無能の人』(91)、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督作品『フラワーズ・オブ・シャンハイ』(98)、賈樟柯(ジャ・ジャンクー)監督作品『罪の手ざわり』(13)等がある。最新作はSABU監督作品『天の茶助』(15)、賈樟柯(ジャ・ジャンクー)監督作品『山河故人』(15)、また、2000年に設立された映画祭「東京フィルメックス」のプログラム・ディレクターを務めている。
矢田部吉彦:仏・パリ生まれ。学生時代を欧州と日本で過ごす。早稲田大学政治経済学部卒業後、大手銀行に就職。フランスとイギリスに留学と駐在で4年間を過ごした後、海外から日本に映画を紹介する仕事に転じる。以後、映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2007年よりコンペティションのディレクターを務める。
【司会】
深田晃司(独立映画鍋共同代表、映画監督)/歌川達人(独立映画鍋会員)
【開催】
2017年4月19日(水)、於下北沢アレイホール
日本を代表する2人の映画祭ディレクターをゲストに招いた今回の鍋講座。この貴重な機会を逃すまいと詰め掛けたお客さんで会場はあっという間に満員となり、これまでの鍋講座で過去最高の159人の動員を記録した。長年の経験で、映画業界の酸いも甘いも知り尽くしたお2人の軽妙かつ大胆なトークに、会場は大盛り上がり。日本の映画文化を支える身として長年現場で奮闘してこられたお2人と共に、映画祭とインディペンデント映画のこれからを探った。
東京国際映画祭:大から小まで、面倒見のよい映画祭

矢田部さんが東京国際映画祭のスタッフに加わったのは2002年のこと。2007年からはプログラミングディレクターとして作品選考を担当している。最初に担当したのは日本のインディペンデント映画を対象にした「日本映画・ある視点」部門(現在の「日本映画スプラッシュ」部門)。現在では、メインの「コンペティション」部門に「日本映画スプラッシュ」部門、そして海外の映画祭で話題になったものの日本で配給が決まっていない作品を幅広く紹介する「ワールドフォーカス」部門の欧米地域担当と、3つの部門のプログラミングディレクターを務めている。
東京国際映画祭は言わずもがな日本で最大級の規模を誇るが、それゆえの悩みも。華やかなレッドカーペットの様子がマスコミで報道されて映画祭が有名になる一方で、一般のお客さんは何だか近寄りがたくなってしまう。誰もがチケットを買って参加できる映画祭であることが意外と知られていない。露出が増えて映画祭が認知されるほど、観客が遠ざかっていく。このギャップを埋めることが矢田部さんにとって長年のテーマとのこと。
ここで昨年の東京国際映画祭のハイライト映像が上映される。たくさんの俳優が集うレッドカーペットや安倍首相のスピーチなど、やはり華やかである。改めて映画祭の大きさを実感した。上映後、矢田部さんから、東京国際映画祭の特徴の一つは「いろんなことをやって、大から小まで、まとめて面倒を見ること」とのお話が。この言葉が、東京国際映画祭を語るうえで後々キーワードとなってくる。
東京フィルメックス:小さな映画のための小さな映画祭

竹中直人監督『無能の人』のプロデュースなど、松竹で活躍されていた市山さんは、1991年にスタッフとして東京国際映画祭に初めて派遣される。担当となったのは、当時の「アジア秀作映画週間」部門。メインの「コンペティション」部門とは別にアジア映画を特集する部門だ。当時の東京国際映画祭で、配給の決まっていない作品を上映していたのはこの部門だけだった。
作品選定を担うことになった市山さんは、手探りの状況から映画祭プログラマーとしてのキャリアをスタートさせる。日本では知られていない良質な映画を観客に届けたいとの熱意から、タル・ベーラ監督『サタンタンゴ』やヴィム・ヴェンダース監督『ベルリンのリュミエール』など、地域の枠にとらわれずに意欲的な作品を次々と上映し、熱心なファンを集めた。この「アジア秀作映画週間」部門はのちに「シネマプリズム」部門へと名前を変え、アジアを中心として、アジア以外の地域からも買い手のついてない面白い作品を発信していった。
「シネマプリズム」部門は映画ファンから大きな反響を集め、会場は満席になることもあったが、マスコミの反応は鈍かった。「コンペティション」部門ばかりが注目されて、その他の小さな部門までテレビや雑誌が取り上げることは少なかったのだ。このままではせっかく上映した貴重な作品が世の中に認知されない。市山さんは次第に、小さく良質な映画を観客に届けたいという想いを、東京国際映画祭という大きな映画祭の傘の下で追い求めるには限界があることを悟る。こうして市山さんは東京フィルメックスという新しい映画祭を創ることを決意する。「大きな映画祭では取り上げられない小さな映画たちのための、小さな映画祭」。それが東京フィルメックスのコンセプトであるとのこと。自分たちの力で資金を集めて第1回を開催したあと、文化庁や国際交流基金の援助を受けて、今年で第18回目の開催を迎える。
2010年からは、東京都や国際交流基金の主催で、ベルリン国際映画祭の「ベルリナーレ・タレンツ」と提携した「タレンツ・トーキョー」を実施している。アジア圏の映画監督・プロデューサーを対象とする人材育成プロジェクトだ。受講生のアンソニー・チェン監督がこのプロジェクトで企画した『イロイロ ぬくもりの記憶』が、カンヌ国際映画祭のカメラ・ドール(新人賞)を受賞するなど、徐々に成果を出している。こうした取り組みを行うのは、「映画祭はただ映画をみるだけの場ではなくて、映画の未来のために何かする場であるべき」という市山さんの信念によるものだろう。
対立する映画祭として見られがちな2つの映画祭だが、それぞれの映画祭がそれぞれの視点と役割を持っていることが大切であると、矢田部さんも市山さんも認識している。東京フィルメックスをもっと大きな映画祭にしないのか、と尋ねられることも多いという市山さんは、「今の規模を続けていくことが大事」と語る。そして、それができるのは、東京国際映画祭という大きな映画祭の存在があるからこそ、とのこと。上映できる映画の数が限られているのはどちらの映画祭も同じで、その枠組みの中で、いかに観客に新たな映画体験を提供するか、いかに多様な映画文化を守っていくか。2つの映画祭は、立場は違えど、映画の未来の発展という共通の目的を見据えている。
そもそもインディペンデント映画とは?
2つの映画祭のコンセプトがうかがえたところで、いよいよ今回の鍋講座の本題である映画祭とインディペンデント映画の関係についての議論が始まる。まずは深田さんから、「そもそもインディペンデント映画の定義とは?」と質問が投げかけられる。普段から当たり前のように使っている言葉だが、実際に定義するとなるとこれがなかなか難しい。
矢田部さんは、「日本映画・ある視点」部門で作品選定を始めたときに、この疑問にぶつかったそう。この部門で上映していた作品と、他の特別招待作品を比べた時に、何が違うのかわからず、部門の存在意義がぼやけたためだ。悩んだ矢田部さんは、選定作品を一気にインディーズ寄りにふる。その結果、受賞したのが2009年の松江哲明監督『ライブテープ』、そして翌年の深田晃司監督『歓待』だった。この2作品の受賞で日本のインディペンデント映画を扱うこの部門の色がはっきりとしたそうだ。ただ、インディペンデント映画部門となるとすぐに若手支援の部門と連想されてしまうが、実際は若手でなくとも、かつての若松孝二監督のようにインディペンデント映画をつくる監督はいる。予算や年齢の問題ではなく、作り手の意思が明確に感じられる作品であることが、インディペンデント映画の一つの定義なのではという結論になった。
メジャーとインディペンデントの共存の場
では、そのインディペンデント映画を映画祭はどのように広めていくか。矢田部さんはメジャーな大作もインディペンデント映画もどちらも含んでこその映画文化であると言う。市山さんからは特別招待作品の山が東京国際映画祭のカラーを見えにくくしているのではとの指摘があったが、矢田部さんはそこにジレンマを感じつつも、ポジティブにとらえている。そういった大きな作品を上映しないとマスコミやスポンサーは振り向いてくれないという面もあるが、同時にそれは、メジャー作品を目当てに来たお客さんが、同じ会場で上映されているインディペンデント映画を新しく発見してくれるかもしれないからだ。この東京国際映画祭の特徴を象徴するエピソードとして、映画祭のチラシで『アデル、ブルーは熱い色』の隣で紹介されていた作品が『プリキュア』だったとの逸話(!?)も披露された。
日本のインディペンデント映画の現状

ここで司会の歌川さんから、「映画祭を目指すうえで、今の日本の映画作家に不足している点は?」との質問が。映画祭ディレクターとして率直な意見を聞きたいところだ。市山さんからは「日本の監督はいい意味でも悪い意味でも、商業映画をつくろうとしている。つまり、どこかでみたような映画が多い」との意見が出る。映画祭と言うフィールドではそうした商業的な目線でつくられた映画はどうしても弱く、落とされてしまう。海外からの応募作品と比べたときに、目立つのは映画の斬新さ、極端さの差だ。矢田部さんも、とにかく日本の映画は学園ものや青春ものが多すぎると語る。もっと成熟した物語が多くてもよいとのことだ。
助成金について
深田さんからは、「中国の映画もウェルメイドな作品が多いが、それは政府の検閲があるから。日本だと中国ほどには検閲もないはずなのにそうした無難な作品が多いのは、やはりすべての作品が構造的に高い商業性を求められるので、言うなれば”経済的自主検閲”があるからではないか?」との意見が出る。これに対して市山さんから、日本では商業的要素を排除して映画をつくるための助成金システムがうまく機能していないとの答えが。今のところ、日本には低予算映画に対する助成金がないため、フィリピンのように助成金だけで映画をつくることは困難。また、公開されそうにない映画でも、完成させることに意味があるから助成金を出すという考えのフランスとは対照的に、日本の助成金システムは成果物主義になっているとのこと。税金を投入するからには万人に広く観てもらえる映画、つまりある程度の制作費がある映画ではないと助成できないという考えが一般的である。だから、一番の問題は、助成金を申請する際に映画の予算に下限があることで、芸文振の劇映画の助成金の場合5,000万円以下の規模の作品だと、助成金の申請もできないのが現状だ。また、応募できる機会も、フランスでは年に4、5回あるのに比べ、日本だと年に2回だけ。国際共同制作への助成金に至っては年に1回しか応募機会がない。
企画開発や、配給をサポートする助成金も必要だ。東京フィルメックスでは「タレンツ・トーキョー」の卒業生を対象に、50~100万円で脚本に対して助成金を出しているとのこと。徐々に助成金システムを使いやすくするための動きはあるものの、継続して政府に働きかけること、声を届けることが重要だ。
レンタルDVD市場の変化、ビデオ・オン・デマンドの勃興
そしてもう1つ、日本のインディペンデント映画が苦境に立たされている理由として挙げられたのが、レンタルDVD市場の崩壊だ。2000年頃には一万店ほどあったレンタルDVDショップが、今では数をどんどん減らして数千店ほどになっている。また、以前はDVDを店頭に置く際に、買取制が一般的だったが、2006年頃からは売り上げに応じて利益が分配されるシステムに移行してしまった。DVDの回転率が悪くてもある程度の売り上げを確保できた昔と違って、インディペンデント映画にとっては苦しい現状になっている。以前は予算を組むうえで頼りにしていたレンタルDVDでの売り上げ分が、今ではすっぽりと抜けてしまったのだ。
会場からは、アマゾンやネットフリックスなどの配信プラットフォームがこれからインディペンデント映画に与える影響について質問もあった。市山さんによると、そういったVOD(ビデオ・オン・デマンド)で、注目され、多く視聴されるのは結局メジャーな大作だとのこと。また、現在各地の映画祭でアマゾンやネットフリックスが大量に作品を買っている。これはプロデューサーや監督にとっては嬉しいことで、映画館のない地域まで作品を届けられることは素晴らしいが、日本のようにアートシアターが充実している国では、配給会社が苦しくなるとのことだ。矢田部さんからは、VODの客層と映画館の客層には違いがあって、VODで埋もれてしまう作品もあるとのお話が。例として、ショーン・ベイカー監督『タンジェリン』はネットフリックスで公開したあとに、イメージフォーラムで劇場公開された。VODと映画館が共存できる可能性もあるかもしれない。これからVODが映画界にどのような影響をもたらすかは、もう少し様子を見る必要がある。
映画祭が後押しできること

映画祭とインディペンデント映画の関係に話を戻そう。矢田部さんは、映画祭に出品されることが、監督にとって果たして本当に幸せな道なのかどうか最近考えてしまう。商業的な経験を積んで成長する監督も現にいるからだ。そこで深田さんに対して「映画祭で有名になるのと、大衆受けして商業的に大ヒットの映画をつくるのと、どっちがいい?」との大胆な質問が。深田さんは「商業的に小さいマーケットの中でやっていくには、自分の映画を楽しみにしてくれる、自分の観客を育てることが大事。そのために、映画祭は選び賞を与えることでバックアップしてくれるから、とてもありがたい」とのことだ。「映画祭は映画が市場に出ていくための後押しの場」とも深田さんは語ったが、実際それぞれの映画祭は、出品された作品を後押しできている感覚があるのだろうか?
矢田部さんは、「配給のついてない作品を重視しているし、その作品が映画祭を経て配給が決まると嬉しい」と語る。また、商業的価値の低い作品でも積極的に上映するのは、映画の多様性を守るためとのことだ。しかし、実際は年々欧米系のインディペンデント映画を劇場公開することが難しくなっている。新しい観客が育っていないことがその理由ではないかと言う。
市山さんも、配給が決まりそうなものを映画祭が選ぶのは邪道であり、自分の映画祭で上映した作品が劇場公開されると嬉しいという。例えば2011年に最優秀作品賞を受賞した内田伸輝監督『ふゆの獣』は、もともと劇場公開の可能性は薄かったが、東京フィルメックスでの上映もあって劇場公開を実現できたとのこと。しかし、劇場公開まで持っていくことはなんとかできるが、そこから先が難しいと市山さんは言う。上述した様々な困難のせいもあって、年々インディペンデント映画を取り巻く状況は厳しくなっている。
「作られる映画の数自体が多すぎる」との指摘も矢田部さんからあった。10年前は1年に劇場公開される映画の数は日本で500本ほどだったが、現在は年間1200本ほどになっている。この作品数の増加は世界的な現象らしく、海外の映画祭で取り上げられる日本映画が少ないのも、向こうの映画が多すぎて順番が回ってこないという一面もあるとのこと。また、助成金システムが弱いうえに労働基準法が緩い日本では、個人の過重労働に頼ってどうにか映画を作れてしまうため、製作本数が増えてしまうのでは、との意見もあった。
観客を育てるために
作られる映画の数が増加するのに対して、映画を観る人の数は減ってきている。国民1人あたり1年に映画館で観る映画の数は、フランスは4本ほどであるのに対して、日本では1.3本。フランスの年間劇場公開数は200本と日本のそれよりずっと少ないのに、1人が観る映画の数は日本の3倍もある。日本ではたくさん映画が公開されるのに、観る人が少ないのだ。新しい観客を育てることは必要不可欠な課題だ。そのために、映画祭はどのような取り組みをしているのだろうか?
東京フィルメックスでは毎年1本は子どもでも観られるような作品を上映しているとのこと。子どもに呼びかけてそういった映画を観にきてもらうようにしている。また、U-25割引も実施して、若い観客を呼ぼうとしているとのことだ。東京国際映画祭では学生のチケット代を500円にしている。また昨年はユース部門で若手映画を3本特集するなど、若い観客にむけての取り組みも行っている。「映画を好きになってもらうきっかけとなる映画を選ぶのは難しい」と矢田部さん。そういった意味で、東京国際映画祭は、『君の名は。』のような大作から、ジョアン・ペドロ・ロドリゲス監督『鳥類学者』といったインディペンデント映画まで同じ会場で上映しているので、普段交わらない客層が何かの偶然で交差して、新しい映画に出会うことを期待している、とのことだ。
おわりに
映画祭の運営から助成金などのインディペンデント映画を取り巻く現状まで、様々なテーマを扱った今回の鍋講座。ゲストのお2人によるタブーなきトークに、会場からは終始笑いが絶えなかった。どちらの映画祭もまだまだやれることはあると市山さんも矢田部さんも語る。状況は苦しいけれど、お2人ともそれぞれの立場で闘っていることを実感した。映画祭は未知なる作品や人との出会いの場であり、映画の未来を育む場である。会場からは「もっと映画祭に足を運んで応援しましょう」との意見がでたが、まさに私たちがすべきことは、安易な批判の前に、積極的に映画祭に関わって映画祭を育てていくことだ。映画祭はいつだって、確固たる意思をもったインディペンデント映画と、映画の将来を支える観客たちを待ち望んでいる。それならば、私たち作り手や観客にできることはまだまだあるだろう。そう前を向きたくなるような今回の鍋講座だった。(レポート:新谷和輝)