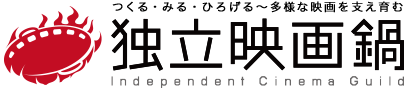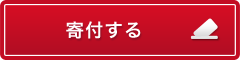トークイベント「女もつらいよ!?日本映画と現場のリアル~映画・仕事・子ども~」レポート PART2
 PART1につづいて、PART2のレポートです。
PART1につづいて、PART2のレポートです。
PART2「海外からゲストを交えて」
続いての第2部では、第29回東京国際映画祭に来日中の、海外からのゲストをお迎えして、グローバルな視点から語り合いました。
フィリピンからは「アジアの未来」部門上映作品『バードショット』プロデューサーのパメラ・L・レイエスさん。
ドイツからは、コンペティション上映作品『ブルーム・オヴ・イエスタディ』プロデューサーのカトリーヌ・レンメさん。
このお二人に加えて、来場中の映画人の方々からも、貴重なご意見を伺うことができました。通訳は、独立映画鍋理事の藤岡朝子さんがつとめてくれました。
各国の現状は
それぞれの国の映画産業におけるジェンダーバランスについてから、トークはスタート。
レンメ:私は二人の子供の母親で、子供は12歳と15歳です。
ずっと私は映画界で仕事してきました。今日は自分なりの意見が言えればと思います。
レイエス:今まで2回東京国際映画祭に来たことがあります。私は、26歳でまだ子供はいませんけれども、映画産業において女性がどういう働き方をしているのかは、知っているのでお話できます。
深田:各国の映画産業におけるジェンダーバランスについては、いかがですか。
レイエス:実数は分からないけれども多数の女性がフィリピンでは働いています。
ジェンダーバランスは、女性が、全体の半分より、ちょっと少ないくらいです。
深田:それは日本の男女比率に比べてかなり多いですね。
レンメ:ドイツでは、ジェンダーバランスはセクションごとに違うので、一概に言えないですが、女性はプロデューサーが多く、監督は少ないですね。映画学校での男女比は半々くらいですが。
女性の視点を世の中に反映させていくためには、やはり女性監督を増やすべきです。
そのためにどういうサポートをしていくのかが、今、わが国では議論されています。
女性の雇用は男女比でいうと、プライムタイムのTVのディレクターをしている女性は全体の約11パーセント、映画監督は全体の約22パーセントが女性ですね。
しかし、予算規模の大きい映画作品での統計は、女性監督が約11パーセントと言う比率になってしまうんです。

レイエス:フィリピンでは、女性は映画産業のほうが、テレビ業界よりも数多く働いています。
女性がついている職種はプロデューサー、プロダクションマネージメントや助監督的な役職が多いです。
総体的に女性はマネージメント担当、男性がクリエイティブ担当になっている傾向が強いです。
深田:バランスでいくと、女性のディレクターが少ないですね。
また映画学校における男女比とは実際に違ってしまうのは、どういった要因ですか。
レンメ:想像するしかないのですが、石井さんが抱えている問題とドイツの女性たちが抱えている問題は、実は同じなのではないか、と思います。
そして、感心したのは、今日、この場に来場している男性の数がとても多い、と言うことです。
こういう場合、ドイツでは、だいたいは女性たちのみで集まって話し合うことが多いのです。
でも先ほどのPART1のお話を伺っていて、気づいたのは、日本の映画産業における、子育て支援のための未来のイメージの中に、父親の存在が不在であることです。
もしかしたら日本の父親や男性たちは、ドイツほど、社会から責めたてられていないのかな、と思います(笑)。
石井:そうですね。 日本においては、男性に対して社会はそういう部分があるかもしれません。私も、夫の後に三歩下がって…という感じです。
それは日本全体の問題かも…。
また男性が基本的に育児に参加しない、というのも日本の大きな問題なのかもしれません。
私の周りで現場に参加できている人は、パートナーが家事や育児に協力してくれる人が多いですね。
そうでない方も日本には大勢いるんです。
レイエス:PART1の話題は、私には新鮮でした。
フィリピンでは、実は、この問題はメイドさんを雇うことで解決できるのです。
メイドを雇って育児中の母親が子供をあずけるのは、私たちの国ではそれほどお金がかかりません。
また、女性は子供がいるからといって就業が難しいということは、フィリピンではありません。むしろ若い女性よりも人間として成熟している、とされて社会で重用される傾向があるかもしれません。
深田:お子さんがいることで、信頼度があがるんですか。
レイエス:子供がいることは、成熟と信頼の証とされるので、映画産業でもその他の仕事でも雇用に差し障りが出ることはありません。

ここで、会場を訪れていた、インドネシアの女性映画監督プリタギタ・アリアヌガラさん(「アジアの未来」部門上映作品『サラワク』を監督)から発言がありました。
アリアヌガラ:今の話を聞いて思ったのは、プロデューサーなどは子供を預けることができるでしょうが、監督の仕事は朝9時から17時までで終わり、というわけにはいきません。
仕事が夜遅くなって家に帰れないこともあるし、今週と来週ではまったく仕事のルーティーン、就業時間が違うといったこともある。
規則的な生活ができないのが監督の仕事です。一方、子供には規則的な時間の生活が必要だと思うんです。
続いて、インドネシアのプロデューサー、デウィ・ウマヤ・ラフマンさん(「アジアの未来」部門上映作品『サラワク』プロデューサー)から以下のような発言が。
ラフマン:私には3人の息子がいます。そして、映画界で15年間働いてきました。
以前、ラインプロデューサーをしていたときは、生後一ヶ月の子供を現場に連れて行って働いていました。
編集の仕事をしていたときは出産直前の状態でも、仕事をしていました。
そして、出産後に、一ヶ月休んでから、職場に戻りました。
インドネシアでは、女性が映画界のジェンダーバランスの30パーセントを占めています。
私たちは、スタッフを雇用する際は、その人自身を見て、仕事をお願いします。
その人が妊娠や出産ということになれば、それにきちんと対応するという発想です。
実際に現場で他のスタッフが母親に代わって赤ちゃんの面倒を見たり、出産直前の女性スタッフがチームにいれば、以前香港で撮影していたときなどは、香港の病院で診察が受けられる体制を整えたりしています。
また、今回の東京国際映画祭で来日しているカミラ・アンディニ監督(カラフル! インドネシア部門『ディアナを見つめて』を監督)の過去の作品で、アリアヌガラは助監督でした。
そのとき、アンディニ監督は妊娠7ヶ月。先に生まれた一番最初のお子さんも幼かったです。
そこでアリアヌガラはお子さんの面倒をみたり、アンディニ監督の話し相手になったりしていたんです。
深田:石井さん、いまのお話を聞いてどうですか。
石井:いいなあ、私もそんなところで働きたいなあ。
私も妊娠7ヶ月のときに、ある短編映画の助監督をしたことがありますが、そのときは朝の4時まで働きました。…死ぬかと思った…。

レンメ:父親の話題に戻すと…。
ドイツでは、子供を生んだ母親は仕事ができない1年間、金額は大きくないですが、政府から補助金が出る制度があります。
さらに今は、父親が育児休暇をとり、それに対して政府から補助金が出る、というように改正されたのです。
以前は男性の働く会社の上司が、自分の部下の男性が育休をとるなんて、想像できなかったでしょう。
石井さんのお話では「若い女性は、出産育児におけるリスクがあるので、雇用する側が嫌がる」ということでしたが、育児に男性も参加する、という慣習になれば、男女の雇用機会の差はなくなるではないでしょうか。
しかし、先に述べた法改正後も、男性たちは実際には育休を取らなかったのです。
なかなか現状が変わらないので、ドイツ政府はさらに二ヶ月分補助金の支払い期間を延ばしますよ、と法律をさらに改正しました。
そうしたら、ドイツの男性たちはようやく、育休を取り始めました。
深田:ここに座っているのが、肩身が狭くなってきました(笑)。
レンメ:気にしないでください(笑)。
レイエス:フィリピンでは、映画産業に携わっている人たちは、ほとんどフリーランスです。
会社に雇用されているわけではないので、作品・企画ごとの契約です。
労働組合がないので、彼らの労働を守ってくれる制度もないんです。
制作会社は社会保障を負担しなくてすむので、フリーランスの人材を雇用したがる傾向があります。
また、労働時間が長いという状況は日本に似ていると思います。
政府からは、1日8時間から12時間労働にしなさいというお達しがあるのですが、それをチェックする制度などがあるわけではないです。
現実には、政府推奨の労働時間は守られていません…。
そういう意味では日本で似ていますね。スタッフたちが制度で守られていないということが…。
深田:確かに、日本とフィリピンは似ていますね。
かつて日本では、黒澤明監督や小津安二郎監督が活躍した映画全盛期のころ、スタッフもキャストもすべて映画会社の社員でした。
しかし、それらの映画会社のスタジオ解体後は、そのほとんどがフリーになってしまった。
日本にも、映画全盛期に作られた歴史の古い組合が残っているのですが、やはりこの組合は現在の大手映画会社の社員にしか機能できていない現状があります。
また、テレビ局の社員の労働環境についてはときどき厚生労働省のチェックが入っても、実際に番組を作っているのはテレビ局が発注する下請けの番組制作会社だったりします。
そこでは過重労働のスタッフたちが、実際の番組作りを支えています。
女性へのハラスメントは
深田:映画への女性スタッフへのハラスメントと、その問題への取組みの現状を教えていただきたいのですが…。
レンメ:…答えにくい質問ですね。あるかもしれないが…ないともいいきれない。なかなかオープンにそういう話題にはならない状況が、ドイツにはあるのです。
私自身は、個人的にそういう経験をしたことはないです。
深田:「ない」と言うお話が聞けてよかったです。
自分自身が映画の現場にいると、とても目に付くのです。
日本では、欧州なら普通にレッドカードものの、セクハラやパワハラが横行していると感じます。
「そうではない」と言う話が聞けただけでもよかった。
レンメ:もし私がプロデューサーの現場で、そういうことをした人間がいたら、即刻クビになるでしょう。
レイエス:セクハラは、私には目にしたことはないですが、パワハラはありますね。
特に女性が何か意見を持つ、つまり「こうしたい!」と意志表示することが好まれないですね。
これに対して、男性が自分の意見をいっても、周囲から抵抗は生まれません。
でも、女性が自分の要求を口にすることは、受け入れられない。
フィリピンは父権性が強いというか、男性中心の考え方、マッチョイズムがあり、男性を立てるという文化がある。
そのため、女性に権力があるという状況は不自然とみなされる傾向があります。
人によっては、女性が力を持つことを、男たちのプライドが傷つくことだと感じる人もいますね。
石井:それを聞くと日本と似てるのかな、と思います。
そしてここで、会場を訪れていた、インドの女性映画監督アランクリター・シュリーワースタウさん(「アジアの未来」部門上映作品『ブルカの中の口紅』を監督)から発言がありました。
シュリーワースタウ:インドの映画界の現状について話します。
助監督であることと子供を持つこと、この二つを両立させることはインドでは不可能です。
監督、プロデューサー、ヘアメイクなどの職種は育児をしながらでも、できます。
インド映画界の職種のなかで、助監督は特に大変な仕事と思います。
また、助監督は、インドでは一生続けるべき仕事ではない、と考えられています。
つまり、ある年齢になったらプロデューサーになるのか、監督になるのか、または会社に勤めるのかなどを選択するまでの役職という位置づけです。
セクハラについては、残念ながらインドではよく見られますね。それは特に、上昇志向の強い女優へのセクハラが強いです。
カメラの後ろ側、つまりスタッフに対してはそれほどではない。インド映画界では、女性スタッフは今非常に増えてきています。
一方、撮影現場で、女優を見る男性たちの目には非常に危険を感じるときがあります。
女優たちがセクハラにさらされている気がするのです。
女性監督は増えてきており、ジェンダーバランスの女性の割合は上がってきています。
しかし、私が問題だと思うのは、いっぽうで女性の撮影監督たちが、なかなか子供を持てないということです。

ここで、会場を訪れていたカメラマンの日本人男性の方からご意見をいただきました。
男性:私は、これまでの人生で、女性をあえて起用して、アシスタントとして育ててきました。しかし、道半ばにして結婚と子育てで、皆辞めていくんです。知り合いの女性の撮影監督も結果として未婚または子供がいない、と言う現状です。テレビ業界では少し改善されているようですが、映画は女性カメラマンはインドと同じ状況です。
さらに会場から、こんな意見が…。
お子さんを持つ女性映画プロデューサー:企業や国単位で、この問題は改善すべきと思います。労働時間も含めて…。
今年、10日間映画撮影のため、自分の子供を親にあずけてフランスに行って来ました。
フランスでは8時間労働は徹底していて、私はプロデューサーなので「もっと働いてよ」とも思うんですが、皆さん朝も元気だし、労働のパフォーマンスが高いです。
日本の映画の撮影現場ではときに1日中働いて2時間寝て、というのが毎日続いて、みんな疲弊していきます。
これはよくないんじゃないかなというのを、フランスで学ばせていただきました。
また、アシスタント時代に私はアメリカで撮影をしていたんですけど、ハリウッドはクルーに対しては、ベビーシッターを雇用して、撮影現場でお母さんが働いている間、赤ちゃんの面倒を見ていました。
日本もそういう風になっていったらいいな、と強く感じました。
その解決方法として、やはり子育てや男女平等という意識改革が必要だな、と思います。
男性がこの会場に多いのは、すばらしいと思います。
深田:今、ドイツのお話を伺って、日本にはそういったきちんとした制度がないなと思ったのと、PART1でもあった「統計を取ることが必要である」という、数字で証明していく作業。それが日本映画界では全くなされていないです。
労働実態の統計なども取られていないので、それが必要だな、と。ドイツにおいては、どちらの省庁がそういった統計を実施しているのですか。
レンメ:ドイツの映画監督協会が国全体でリサーチして、ロストック大学という大学が研究発表をしています。
また支援は、家庭省というのがあり、そこが支援を行っています。
でもあえて釘をさしておきたいのは、テレビでは11パーセント、映画でも22パーセントの女性監督しか活躍できていないこと。決して、現状はバラ色ではないです。
深田:日本の現状が余りにもひどいので、目の錯覚でよく見えてしまっているのかもと思います…。
根来:私はかつて、5世帯程ほどが一緒に住める都心部のビルでハウスシェアしてました。
そこではかつて、三人のシングルマザーと子ども達と独身の男女が共同生活をしており、母親たちはビラをつくり、保育に無償で協力してくれる人々を集めていました。
仕事や余暇で家をあけるときは友人や同居人たちに保育をお願いし、三人が上手く協力者のスケジュールを調整することで自分のキャリアや目的と上手くバランスをとっていたと思います。
ポジティブなムードがあり、多くの人が自然に集まる場所でした。
それぞれの立場で
イベントに、そろそろ終わりの時間が近づいてきて…。
最後にそれぞれが、自らの言葉で総括的な意見を語りました。
石井:今回、いろいろ勉強になりました。今度皆さんが日本に来ていただけたときには「日本にこんな制度ができてて、すごいね、あたしも勉強しなきゃ」と言ってもらえるようにしたいと思います。一緒に活動してくれる方がいると心強いです!
シュリーワースタウ:インドの女性スタッフは自分の属する社会階層や経済状態のおかげで特権的な暮らしができています。
インドは、社会階層と経済環境がよければ何でも解決できる社会です。
自分の所属する階層で暮らしやすさ、暮らしにくさが決まる部分があります。
逆に低い階層の人でもヘアメイクの仕事ならば身を立てていける。そういう映画界への入り口もあります。
ラフマン:インドネシアは、制度が整備されていない国です。
女性同士がサポートしあうことが必要だな、と思いました。
私自身プロデューサーですが、スタッフを雇用するときは妊娠やお子さんの有無で見るのではなく、仕事の決断力や創造性を重視して選ぶようにしています。
これからも、そうありたいです。ひとえに作品をよりよくするためです。
アリアヌガラ:私は映画の仕事を12年やってきました。
私は独身ですが、このイベントに参加できて感謝しています。私にできることは境遇が違っても助け合うことかな、と思いました。
助け合いの際には、それぞれの人が、自分で、必要としていることを提示していくことだと思います。
レイエス:私もスタッフに求めるものは、ジェンダーやお子さんの有無ではなく、その人のクリエイティビティです。
ジェンダーに、上下はありません。そして、常に他者を尊重することが大事だと思うんです。
「please」と「sorry」は、いつも忘れないようにしています。
高圧的、権威主義的な態度は廃していきたい。映画界に関わる人たち、すべての生活のありようがより良くなって欲しいです。
レンメ:ジェンダーに上下はない、というのはまったく同感です。『ブルーム・オヴ・イエスタディ』を製作した際、実は、メイク、音響、録音以外のセクションのトップはすべて女性のスタッフだった。
この作品のクリス・クラウス監督、は自分を「フェミニストです」と言うようなタイプの男性ではない。
しかし、あえてそうなったのは、ひとえに彼女たちと仕事をしたい!と思ったからです。
彼のような人間こそ、私たちの未来ではないでしょうか。
もっと、こうしたことが増えていって欲しいと思いますし、このような立場の女性が増えればセクハラも減っていくのでは。また、人材の搾取の動きも減っていくでしょう。
石井:皆さんと会えて、とても幸福です。これからも、男女、子育て、関係なくよい映画が創りやすい環境になってほしいです。
深田:今回、企画してみて…。
多くの女性の方たちのサポートのおかげで、今回の企画が成り立ったんですけど、そのなかで、大きな気づきがありました。
各国の皆さんが取り組んでいることがある、という事実を知れたこと、そして、この2時間が皆さんにとって、持ち帰っていただける発見や気づきがあればいいな、と思っております。
男女問わず、今後この問題について考えていかないといけないし、日本の男性はまだ女性から責められてない、甘やかされているのかな、と思いますので…。
男性たちからの自己批判も、より必要なのかな、と感じました。
2時間以上にわたる熱いトークイベントで、さまざまな発見があり、また、今後の課題が浮き彫りになりました。
登壇者の皆さんは、それぞれの思いを胸に、今後も映画界を歩んでいくことと思います。
こうした課題を解決していくには、私たちひとりひとりが、身近な、自分ができることから、まず、始めていくことが大切なのかもしれません。
実は、今回のレポートを書かせて頂いている私自身も、かつてこの世界に入った頃に、現場で、理不尽かつ壮絶なパワハラを受けており、今でも消えない怒りと憤りを持ち続けています。
一時はこの業界から去ることを、真剣に考えるほど悩み、苦しんだこともありました…。
深田監督が現場で具体的に対策を実践されていると伺って、嬉しく思いました。
私も現在、自分がプロデューサー、または監督で入っている作品の現場ではパワハラ禁止、セクハラ禁止はもちろんですが「終電までに必ず現場完全撤収」を基本に行っています。
この4年ほど、年平均6作~8作ほどの作品を創っているのですが、実感として、事前の段取りをきちんとして、現場滞在時間を無意味に延ばさず、楽しく進行したほうが、作品のクオリティにもよい影響が出ていると思います。
こうしたことを、各現場で実行する人たちが増えれば、業界全体の改善に、一歩一歩近づいていくのではないでしょうか。
ひとりひとりの取り組み、それ自体は小さな一歩かもしれません。
しかし、大勢の人たちが踏み出し、歩んでいけば、それはしだいに大きな足音となって社会に、そして、世界に響いていくのではないでしょうか。
(文責・上本 聡)

このイベントの動画はYouTubeで見られます。