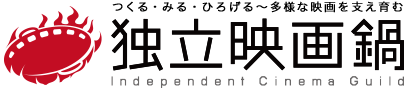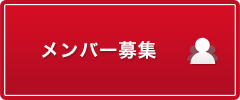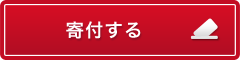鍋講座vol.54【パンフをつくりたい!~インディペンデント映画のパンフレットが観客に届くまで~】レポート ―映画とつくり手に対する愛情の賜物―
宣伝予算が限られるインディペンデント映画では、パンレットが観客の手元に届くまでにどんな過程を経て、どんな工夫がなされているのだろう。その問いに答えるのが、6 月に開催された鍋講座「パンフをつくりたい!」だ。登壇者は、配給・宣伝を手がけるインターフィルムの相川智さん、宣伝そして編集を手がける平井万里子さん、映画鍋会員でもあるグラフィックデザイナーの鈴木規子さん。さまざまなパンフレットを世に送り出している3 人に、具体的な事例を用いた資料をもとに詳しく解説していただいた。このレポートではその内容を項目別に要約し、できる限りお伝えしていきたい。

■パンフレットの制作工程について
スケジュール
映画の公開日が決まると、逆算して宣伝ツール別(ポスター、チラシ、試写状、前売り券、公式サイト、パンフレット)に制作スケジュールが割り出される。パンフレットの制作はいちばん最後になる。相川さんによると、目安として公開日の2週間前に入稿、その3週間前に初稿アップ。遅れることもあるので、それを見越してスケジュールを立てるそうだ。ギリギリの場合、入稿が劇場納品日の3、4日前ということもある。デザイナーへの発注は初稿の3週間前から素材を送り始めるが、初稿アップ時に素材が揃わないページもあるようだ。
制作の決定
宣伝予算の都合でパンフレットを作らない場合もある。平井さんによると、1週間限定公開で劇場が1館しか決まってないというような場合は、費用対効果を検討してパンフレットの制作を断念することもあるそうだ。ただ、デビュー作などの場合は監督の思い入れも強いので、その意志を尊重して作ることにしている。近頃、造形や仕様に凝ったパンフレットが人気を博していることもあり、そういったものを望まれることがあるという。凝った仕様のものは巷の印刷会社に発注し、色校正もしっかり行わなければならないのだが、インディペンデント映画では安価なネット印刷が主流だ。印刷費にそこまで詳しくない監督のために、まずはそういった実情を説明して理解してもらうところからパンフレット制作が始まる。
関わる人たちに発注
制作には様々な人が関わっている。まずは編集担当。これは宣伝の人が兼務することもある。そしてデザイナー。通常はポスターやチラシを手がけた人が担当するのだが、鈴木さんによると稀にパンフレットだけ頼まれる場合もあるそうだ。イントロダクション、あらすじ、インタビュー等は、公式サイトやチラシ制作の段階から執筆するライター、いわゆるオフィシャルライターに引き続き依頼することが多い。レビューの執筆は、マスコミ試写等で作品を気に入ってくれた人に依頼するケースがほとんどだそう。
パンフレット制作を丸ごと外部に委託するケースもある。例えば、キネマ旬報や松竹にはパンフレットを制作する部署があり、最近ではナカチカピクチャーズでもそういった部署を立ち上げている。その場合、作品のことを一番よくわかっている配給や宣伝と全てを共有し、マインドを同じにしなければならない。
台割りの作成と打合せ
台割りというのは、パンフレットのページごとに何が入るのかというのを可視化したもの(全体のボリュームは費用にも関わることなので、台割り作成前に目安を決める)。平井さんが宣伝と編集を担当し、鈴木さんがデザインを手がけたアニメーション映画『音楽』のパンフレットは100ページにも及ぶ。そのコンセプトは、「アニメーション映画によくある原画集みたいなものとは一線を画したい」という岩井澤健治監督の思いを尊重し、読み物を中心にするということだった。台割りは監督の自伝的エッセイ、作品に関わったスタッフの方々のインタビュー、時系列順の制作過程、鼎談、原作者である大橋裕之さんの描き下ろし漫画等のページで構成されている。
また、インディペンデント映画ではシナリオを掲載するのが主流となっている。シナリオがあるかないかで売上が変わってくるので、とても大事な要素の一つだ。シナリオのテキストデータをデザイナーが受け取りページ数を割り出す。
完成した台割りをもとにデザイナーを交えて打合せを行う。表紙のイメージ、判型、スケジュールなどを話し合う。文字が縦組みなのか横組みなのか(それによってパンフレットが右開きか左開きかも決まる)といったことも映画のイメージによって決めるようだ。パンフレットのデザインコンセプトはこの段階で決まる。平井さんによると『音楽』のような大ボリュームのものを目指す場合は、デザイナーのスケジュールの確保が重要になるため、台割りを作成する前に伝えるそうだ。
デザイン作業と原稿執筆
デザイナーが台割りから割り出した大体の文字数をもとに、編集担当が原稿の執筆をライターに依頼する。メインキャストのプロフィール等は、公式サイトや作品資料用にすでに作成しているが、劇場公開時にはキャストの新作情報が更新されている場合がほとんどのため、追加で赤字をもらう必要がある。また、サブキャスト、スタッフのプロフィールは新たに作成する。
使用するキャストたちの画像には所属事務所のチェックが不可欠。OK画像の選定は宣伝が行うのだが、現場でチールカメラマンによって撮られたキャストたちの写真は合わせて10,000枚に上ることもある。キャストごとにフォルダに振り分け、事務所とのやりとりを経てNGカットをはじき出し、OKカットを絞り込むという過程を踏む。予めOK画像が決まっていない場合はデザイナーが選定し、初稿の段階で事務所の可否を問う。
本編の場面画像は現場でスチール撮影したものを使用することがベストだが、小規模の作品だとスチール素材がないこともある。その場合はデザイナーや編集者、監督が本編からキャプチャーするのだが、その解像度によっては問題が生じる。鈴木さんによると、フォトショップで補正することもできるが、カメラマンが撮影した写真とのクオリティの差は歴然としているそうだ。予算が少なくとも、できるだけスチールカメラマンは現場に入れた方が良いであろう。そしてあらかじめ撮影香盤にスチール撮影の時間を組み込んでもらうのがベストだと平井さんは話す。
初稿のアップと確認・修正
初稿が出来上がったら、監督、プロデューサー、配給、キャスト事務所に対して、PDFの状態で確認作業を進める(別途、使用画像を送る場合もある)。並行して編集担当が文字校正、誤字脱字のチェックを行う。事務所からキャストのほうれい線を消すなどの依頼があり、レタッチが生じることもあるようだ。鈴木さん曰く、「完全に消してしまうと不自然なので若干薄くする程度にすることもある」とのこと。
入稿
確認と修正のラリーが続いた後、いよいよ入稿となる。編集担当は最終PDFを確認し、問題がなければデザイナーに入稿データの作成を依頼する。先に述べたように、印刷はネット印刷「プリントパック」や「グラフィック」で行う。入稿作業自体は実費が絡むことなので配給会社が行うことが多いが、編集担当が立て替えて行うこともある。
入稿作業は常に緊張感が伴う。思わぬミスが見つかることもあるので、鈴木さん曰く、入稿の前後3日くらいは油断できないそうだ。思わぬミスでエラーが出て入稿が滞ることもあるようだ。「パンフレットを購入した際に、文字の正誤表が入っていたりすると、自分の仕事じゃなくともいたたまれない気持ちになります」と鈴木さんは語った。
納品と販売
劇場公開の1.5週間前には配給会社へ納品されるのが望ましい。相川さんによると、最初の3日間で観客がどの位入るのか、何割の人がパンフレットを購入するのかを想像して各劇場には発送するそうだ(印刷と販売の項で後述)。劇場によっては様子を見て少しずつ送るようにしている。時間がない時は、印刷元から直接劇場に送ることもあるようだ。
公開初日の舞台挨拶回や、監督や出演者のトーク回の後には、パンフレットの購入者を対象にサイン会が開かれることがあり、多くの売上が見込める。「映画を応援したい」「監督や出演者と話したい」という理由で、サイン会ごとにパンフレットを買う人や、一人で10冊以上買う人もいる。鈴木さんによると、サイン用にスペースを空けることや、黒マジックでサインしやすいように表紙は薄い色にすることを頼まれる場合もあるそうだ。

■内容と構成について
パンフレットの内容・構成は映画によって違いはあるものの、下記のような要素が考えられる。
「イントロダクション」「ストーリー」「キャストインタビュー」「キャストプロフィール」「監督インタビュー・プロフィール」「レビュー・コラム」「プロダクションノート」「スタッフインタビュー・プロフィール」「ロケ地マップ・紹介」「著名人からのコメント」「主題歌の歌詞」「対談・座談会」「人物相関図」「シナリオ」「全クレジット」「奥付け」
講座では具体的な事例を見せながら詳しく解説いただいたが、ここではいくつかの項目について簡単に記したい。
イントロダクション
チラシや公式サイト等、宣伝の立ち上げの時から使っているものを流用することが多い。
ストーリー
イントロダクションと同様に流用する場合もあるが、鑑賞後の観客が読むことを前提に、ネタバレを気にせず長文を載せることもある。
キャストインタビューとプロフィール
キャストのメディア取材の際に、パンフレット用の取材ということで時間をもらい実施することが多い。予算の関係で写真は撮り下ろさないことが多いので、オンラインで行う場合もある。プロフィールは宣伝立ち上げ時にものから更新があるかどうかを事務所にヒアリングする。
監督インタビューとプロフィール
オフィシャルライターにインタビューもお願いするのが基本だが、宣伝担当が聞き手を務め自ら執筆することもある。
レビュー
複数掲載する場合は、執筆者の性別や世代を分けるようにしている。また執筆者ごとにテーマを決めてお願いしている。例えば、Aさんには監督の映像美、Bさんに俳優についてというように。
プロダクションノート
監督あるいは助監督、プロデューサーが書くことが多い。撮影の振り返りを寄稿文として書いてもらう場合と、撮影香盤を見ながら日記形式で振り返ってもらう場合がある。短縮版と長尺版を作成することもある。鑑賞前に読む公式サイトには短縮版を掲載し、鑑賞後に読むパンフレットには長尺版を掲載する(監督インタビューも同様の形を取ることがある)。
スタッフインタビュー
例えば『こちらあみ子』(森井勇佑監督)では、芥川賞作家・今村夏子さんの非常に有名な原作、そして“あみ子”という少女のイメージを監督と共にどう膨らませて映像化したのかを、カメラマンや音響、美術、ヘアメイクのスタッフなどにインタビューし、“あみ子”の多面的な魅力を伝えようと努めた。また『リバー、流れないでよ』(山口淳太監督)では、劇中に登場するタイムマシンを作った美術デザイナーのインタビューを載せている。撮影の合間に時間をもらい、パンフレット用にキャストに入ってもらったタイムマシンのスチール撮影を行った。その写真とデザイン画をインタビューと並べて掲載し、映画を見た人がより深く楽しめるように工夫をしている。
ロケ地マップ
ロケ場所が映画の大きな要素となる場合に掲載することが多い。『雑魚どもよ、大志を抱け!』(足立紳監督)では、舞台となった岐阜県飛騨市の全面協力もと撮影が行われていることもあり、観光協会から提供された地図をベースにロケ場所や地元のお店を紹介している。下北沢が舞台の『街の上で』(今泉力哉監督)ではイラストレターが描いたロケ地マップを載せて、劇中に登場する実在のお店を紹介している。その土地、街が主人公とも言える映画では、街歩きをしてもらいたいという願いがあるそうだ。いわゆる聖地巡礼ということもあり得るだろう。
著名人からのコメント
著名人からの応援コメントはメディア、ニュース等に取り上げてもらい、公式サイトそしてパンフレットにも載せることが多い。追ってコメントが増えることもあり、スペースに余裕を持ってレイアウトを組まなければならないようだ。コメントした人が自身のSNSでも発信し拡散されることに意義があり、コメントを依頼する際にそれをお願いすることも大事である。
対談・座談会
『佐々木、イン、マイマイン』のパンフレットには、内山拓也監督と同作のメイン上映館である新宿武蔵野館のスタッフによるスペシャル座談会が掲載されている。内山監督にとって、同劇場はかつて働いていた場所。平井さん曰く、監督が当時の上司や同僚たちと過ごしたエピソードは宣伝開始当初から聞いており、作品を地でいくような彼らのエモーショナルな日々の振り返りは、鑑賞後のお客さんに必ず共鳴してもらえる、と思っていたのだとか。結果的に、この座談会はパンフレットだけの特別なものとなった。
シナリオ
「シナリオのテキストデータは必ず保存しておいて欲しい」と平井さんは言う。前述したようにシナリオの掲載はパンフレットの売れ行きを左右する。SNS上でも「シナリオがあったからパンフレットを買った」という投稿を目にしたりする。「月刊シナリオ」が作品の規模に関係なく掲載してくれる可能性もあるそうだ。
その他
アニメーション映画『音楽』のシーンにはロック・アルバムのジャケットを模したパロディがあり、そのシーンと元ネタのジャケットの画像を並べて掲載している。『とりつくしま』(東かほり監督)では、小泉今日子さん演じるとりつくしま係の部屋に置いてある小道具を細かく紹介している。『辰巳』(小路紘史監督)では、取材時から度々、監督が「色々なアメリカの映画から影響を受けて同作を作った」と話していたことから、オマージュを捧げた20 作品を紹介するページを設けた。
平井さんは次のように語った。「映画を1度観ただけでは気づかない、もしくは画面に映っていないスタッフの方たちのこだわりを伝えられるのがパンフレット。そういう意味でもパンフレットは充実させたいし、それがリピーターにもつながると思っています」

■経費と印刷部数、販売と売上について
実際の講座ではパンフレットの予算表や販売試算表を見せながら、配給の相川さんに解説していただいたが、ここではその一部について大まかに記したい。具体的な内容をあまり明かせないことをご容赦ください。
デザイン費
デザイナーのギャランティはいわゆる宣伝美術一式(ポスター、チラシ、試写状、前売り券、パンレット等)に対するデザイン料として支払われることがほとんどだが、制作工程の章で触れたように、パンフレットのみをデザイナーが請負う場合もある。鈴木さんによると、パンフレットは2,30ページのものから100ページのものまであり、その作業量によって金額も変わるそうだ。
印刷と販売
プリントパックやグラフフィックの具体的な印刷料はそれぞれのサイトで調べるができる。ここで重要なのは印刷部数の読みである。それぞれ作品のファースト公開館数もとに、動員数とパンフレット購買率(観客動員数に対する)を予測し部数を試算する(公開館数が20館の場合、1館あたり100部を納めるならば印刷数は2,000部になる)。ある作品では3,000部という予測を立てたものの、蓋を開けたら増刷を重ねて7,000部以上を売り上げた。「一度に多くロットを頼むとその分安い印刷代が安くなるので、そこがいつも考えどころです。印刷費を抑えるために、いったん在庫を抱える覚悟を持って一度に多く印刷するのか。売上の様子を見て増刷するのか。最終的には在庫をなるべく減らしたいという思いでやっています」と相川さんは語った。
パンフレットの販売価格帯はページ数によって800~1,200円だ。劇場への卸値はその70~80%になることが多いようだ。パンフレットの売上は、配給収入(興行収入から劇場の取り分を引いたもの。)と同じく、配給会社が手数料を控除し、残りが製作サイドの収入となる(作品によっては監督自らパンフレットの制作に携わっていることもあり、そういった場合はより多く製作サイドに戻すことになる)。人気俳優らが出演する作品では購買率が高くなるし、資料価値の高いものだと購買率が5割を超えるもこともあるようだ。パンフレットの売上は時には大きな収入となり得る。
相川さんはパンフレットの制作についてこう語った。「大変ですけど作った方がいいと思っています。そして、映画をご覧いただいたお客さまがパンフレットを読んで、更に作品へ想いをめぐらせる一助になればいいなと思います。」
■パンフレットをつくる上で大切にしていること
最後に平井さんの言葉を紹介して、このレポートを締めくくりたい。
「お客さんが鑑賞後にパンフレットを読んで、映画を思い出せる内容であることは大前提ですけど、映画に関わった人たちが撮影を振り返ることのできる“卒業アルバム” のようなものにしようと心がけています。将来、何かに行き詰まった時に、すぐに初心を思い出してもらえるような熱量の高いものにしたい、とも思っています。そして、特にインディペンデント映画の監督、キャスト、スタッフはシネコンでかかるような映画と比べると知名度が低いという見方もあるかもしれませんが、パンフレットを通して、その人たちのことをお客さんに知ってもらい、彼らが次に携わる作品も引き続き応援してもらいたい気持ちがあります。映画はさまざまな人の手によって出来ているということ、監督を筆頭に、キャスト、スタッフたちの目には見えないこだわりが詰まっていることを伝えられるのがパンフレット。お客さんにとってもまた、彼らを知ってもらうための “アルバム” みたいなものにしたいと思ってつくっています」
パンフレットは映画とつくり手たちに対する愛情の賜物。その熱量が手にした人に伝わり映画を育んでいくのだ。
文:谷渕新吾