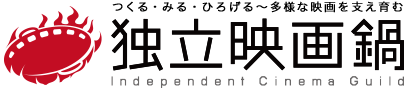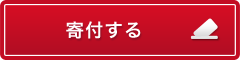【レポート・鍋講座vol.42】「『新しい』を止めない!!ぴあフィルムフェスティバルはなぜ41回続いているか」
40年以上にわたって日本の自主映画シーンを牽引してきたPFF(ぴあフィルムフェスティバル)。昨年8月に行われた鍋講座では、PFFで長年ディレクターを務める荒木啓子さんと、ラテンアメリカ映画の配給や日本の自主映画の海外紹介に力を入れている比嘉世津子さんをお呼びして、急速に変化している映画を取り巻く環境のなかでこれからの映画祭の展望をお聞きしました。42回目のPFF開催が近づいてきたいま、振り返ってみたいと思います。

【日時】2019年8月5日(月)18:30開場/19:00スタート、21:00終了
【会場】下北沢アレイホール
【司会】新谷和輝(映画鍋会員)
【出演】
荒木啓子:1990年PFF参加。1992年よりPFF初の総合ディレクターを務める。コンペティション「PFFアワード」を通して若き映画人の輩出や育成を積極的に行うと同時に、招待作品部門ではダグラス・サーク、ミヒャエル・ハネケのアジア初特集など、映画の過去と未来を伝える企画を実施。近年ではPFF関連作品のみならず、日本のインディペンデント映画の海外紹介にも力を入れ、日本映画の魅力を伝える活動を幅広く展開している。
比嘉世津子:Action Inc.代表。1992年よりNHKスペイン国営テレビ(TVE)通訳。字幕、映像翻訳。スペイン、イタリア、ラテンアメリカの独立系作品を買付け国内配給。2015年、配給10周年として「ラテン!ラテン!ラテン!」のタイトルで配給作品16本を新宿K’s cinemaにて一挙上映。2016年、映画「エルネスト」の台本翻訳、キューバロケで阪本順治監督通訳。3年ぶりの配給作品は、2019.7.13より新宿K’s cinemaにて公開のウルグアイ映画「ハッパGoGo 大統領極秘指令」。
PFFの歴史
まずは、PFFの歴史をざっとおさらいしましょう。1977年に第1回を開催したときは、アルバイト仲間で映画マニアの大学生5人がつくった雑誌『ぴあ』(現在はチケットぴあで知られるエンターテイメントサービスの会社)創刊5年目のタイミングだったそうです。全スタッフが20代の若い映画祭。当時はコンペティションではなく、大島渚監督、大林宣彦監督など、憧れの映画人が審査員となって、彼らが推す作品でプログラムをつくっていくスタイルでした。1988年にコンペティション「PFFアワード」を開始すると、その後の日本映画を代表する数多くの映画作家を輩出していきます。塚本晋也や橋口亮輔などが初期にグランプリを獲得しました。コンペティションとは他にPFFの目玉となったのが、毎年変わる特集上映です。アルノー・デプレシャン、フランソワ・トリュフォー、アレックス・コックス、ホウ・シャオシエンら世界的な映画作家の特集やピンク映画特集を開催しました。その多彩なラインナップは観客を楽しませるためだけではなく、アワードに出品している若い映画作家にたっぷりみてほしいという思いも強いと、荒木さんは言います。

新たな才能を発掘する
荒木さんがPFFに関わりはじめたのは1990年のこと。その後、荒木さんは総合ディレクターという立場について、映画祭の責任者としての役目を明確にしていきます。目指したのは、コンペティションの審査を丁寧に行うとともに、自主映画を日本国内にとどめておかずに、積極的に国外へと送り出していくことでした。
ところで、PFFにおける「自主映画」とはどのような映画を指しているのでしょうか?「インディペンデント映画」や「独立映画」といった、大手以外の映画を指すいろいろな名称があるなかで、荒木さんは「自主映画」という言葉について、個人の「作りたい」という強い意志をもとに作られた映画を意味していると言います。ひとくちにインディペンデント映画といってもその予算規模は様々ですが、PFFが扱っているのはそのなかでも一番小さな、個人の熱意が主体となってつくられる映画なのです。
そうした個人的な映画から才能を見つけ出すために、PFFがとくに重視しているのは審査の過程です。結果を分かりやすく可視化しようと近年各地の映画祭でどんどん要望が高まっているコンペティションですが、PFFは受賞作を決める最終審査員を毎年変えています。審査員が固定されると、映画祭の傾向がだんだんと固まってきて対策を語る人が出てくるからです。また、その前段階にあたる500本ほどの応募作からPFFアワードの入選作を選ぶ予備審査も大切です。審査員の個人的な「好き嫌い」を超えたところ、その映画にどれほどの普遍性が宿っているかを長時間の議論から導き出します。「個人が熱量をこめてつくったものを、できるだけ同じ熱量をもって審査する」のがモットーであると荒木さんは言います。その熱意がよくあらわれているのが、予備審査の段階でほぼすべての応募作品の監督に送られる審査員からのコメントです。ここまでひとつひとつの作品に真剣に向き合っている映画祭は、世界的にも稀有なのではないでしょうか。

近年の自主映画の変化
ここ5年ほどの応募作品の傾向として、映画学校の作品が多くなってきたと荒木さんは指摘します。専門的な映画の技術を学べる場が増えたことで、映画のルックスはプロと大差がないようになってきました。また、昔は誰も予想できなかったこととして、自主映画を映画館で公開することが一般的になったことも挙げられます。
こうした状況の変化にたいして、自主映画の発見・発表の場であるPFF も改めて自身の立場を考え直していきます。2017年には、非営利であることを明言し、運営資金を集めるために一般社団法人となりました。「この映画祭はやめないことが大事なんです」と荒木さんが言うように、個人の才能を見つけ出す貴重な場として、PFFの社会的意義は大きいのです。
また、1984年からはじまったスカラシップも継続しています。当初は8ミリ映画をつくっている人に16ミリという劇場公開可能なフォーマットでプロのスタッフとともに撮らせたいという思いからはじまったこの制度も、その後多数の著名な映画監督を輩出してきました。こういった活動も本来映画祭がやることではないのですが、これからの映画作家のために自分たちがやれることをやるとして、荒木さんは信念をもって続けています。
日本映画の状況
比嘉さんからは世界における日本映画の立場についての指摘がありました。日本映画に対する興味は年々落ちているのを映画祭に参加しながら実感しているとのこと。いまは世界中のあらゆる国で映画がつくられていて、高度な映画教育システムを備えた国や社会的に切実なテーマをもっている国が強く、そのなかで日本映画の存在感はどうしても薄いようです。PFFは入選作品の海外展開にも積極的に力を入れていますが、比嘉さんが言うように英語字幕をつけることが日本の自主映画で習慣化すれば、より世界に届いていくのではないでしょうか。
また、映画祭におけるジェンダーバランスについても話題になりました。PFFでは女性の応募数が少ないけれど、入選者のうちの女性の割合はそれより高いという状況がずっとありました。近年ではさらに女性の応募者・入選者は増えてきていますが、機械的に入選作を男女で50:50にすることは考えていません。それよりも大事にしているのは、創作物に対してフェアであること。そのために、予備審査に参加するセレクションメンバーの構成は必ず男女比は半々になるようにしているとのことです。

なぜ映画祭を続けるか
最後にこのイベントのタイトルでもある、なぜPFFはずっと続いているのかについて荒木さんにお聞きしました。答えとしては、「今年うまくできなかったこと、やっておけばよかったと悔やむことを、来年はこうしようとスタッフ一同で考えているから」、そして「この映画祭はやめないっていう強い意志があってやっているから」というものでした。今回のお話を聞いていて思ったのは、PFFには映画の作り手のための「はじまりの場」というビジョンがいつも明確にあるということでした。その核を大事にしながら、時代の変化に柔軟に対応しているからこそ(近年では、映画祭会場での上映と平行してネット配信上映も行われています)、世界でも稀な自主映画の映画祭としてPFFは存続しているのです。
映画祭とはなんのためにやっているのか。映画産業と映画祭のちがいはなんなのか。誰でも映画を発表でき、どこでも映画を見られる時代の映画祭の役割とはなんなのか。そう考えたときに、映画祭は自由であることが必須である、自由な映画をつくったときに、それを受けとり、楽しめる場所があるということが大事だと語った荒木さんの言葉はとても響きました。自由な作り手のための自由な場として、まさにPFFの精神を体現した言葉です。今年は新型コロナウイルスの影響で各地の映画祭が開催をとりやめたり、オンラインでの上映へと移行しているなか、PFFは自主映画を届けるリアルな場をなんとか維持することを決めました(同時にオンライン配信も行います)。なお、今年の会場チケットは当日券はなく、前売り券のみとなります。これからのPFFの活動に、ぜひ注目していきましょう。(文責:新谷和輝)