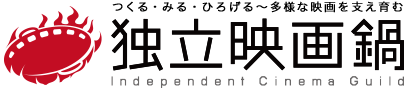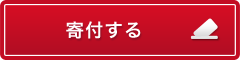NPO法人独立映画鍋主催×第18回東京フィルメックス連携企画 『インディペンデント映画ってなんだ!?』
はじめに
映画鍋共同代表の土屋監督は『インディペンデント映画ってなんだ!?』というタイトルでシンポジウムを企画した二つの理由を挙げた。一つ目は、数年前の映画行政に関する鍋講座で文化庁の人から「独立映画って何ですか?」「自分たちで定義することはできますか?」と問われ、さらに「どうして今、政府が独立映画支援すべきであるかどうかということの理由を、映画業界以外の人にもわかるように伝わるようにきちっと整理してください」と言われたこと。二つ目は、『世界の映画行政を知る』という鍋講座の韓国篇で、KOFIC(コフィック・韓国映画振興委員会)の方の話を聞き、「どうすれば自分たちが考える独立映画の助成システムについてちゃんと説明できるのか」と考えさせられたこと。
このレポートではシンポジウム第一部から第三部までの内容を要約し、登壇者の発言からテーマに対する答えを探っていく。

第一部「日本の映画監督から」
総合司会:土屋豊 ゲスト:内田伸輝 庭月野議啓 聞き手:深田晃司

自主映画を作るということ
一口にインディペンデント映画と言っても様々な形があるであろう。深田監督がゲストの両監督が最新作に至るまでのキャリアについて尋ねた。内田監督は、19歳の時にお金を貯めて作った自主映画からキャリアをスタートさせている。彼は自主映画=自己資金映画であるとしている。その後、ドキュメンタリーの映像制作会社に入り、ニュースの現場でカメアシ、録音マンを担当するが、その過酷さがゆえに半年で退社し、社交ダンスのビデオ制作会社に移る。そこでは撮影と編集を任されるようになり、技術を身につけていく。そして、友人を一人で撮影したドキュメンタリー『えてがみ』(2002)でPFFに入選し、撮影と録音も担当しながら4年半の歳月をかけて完成させた『かざあな』(2007)を経て、最少人数による自主映画の製作スタイルを確立していく。フィルメックスでグランプリを獲得した代表作『ふゆの獣』(2010)と最新作『ぼくらの亡命』(2017)もわずか3人のスタッフで、出演者の都合に日程を合わせて作られており、『ぼくらの亡命』は撮影に約1年かけている。彼の妻でもある、プロデューサー兼撮影監督の斉藤文氏と一緒に資金を集め、主演男優は一般公募し、スタッフ、キャストにはギャラを出せないが、交通費は支給し、手料理による食事を提供するというスタンスで作品を作り上げている。
庭月野監督は九州の大学時代に映画を撮り始め、卒業後、上京しフリーの映像作家となる。その約4年後に撮った短編『イチゴジャム』(2010)がPFFやSKIPシティ等の映画祭で入選するが、それだけでは道は開けないことに気づき、劇場公開を目指して長編を撮ることにする。その作品がフィルメックスにも選ばれた時代劇『仁光の受難』(2016)である。あえて自主映画で時代劇という題材を選び、「海外の映画祭も視野に入れた」と言う。製作資金については、一部、スタッフからの融資とクラウドファンディングによるものもあったが、大半は自ら捻出している。費用が足りなくなると働き、貯まったら制作を再開するというスタイルで、4年の歳月をかけて作品を完成させている。時代劇であるがために、想定より3,4倍の費用が掛かったと言う。
深田監督が「そういった自腹による映画作りの良かった点は何か」「持続することは可能なのか。そのための課題は」と切り込んでいく。庭月野監督は「予算による折り合いをつける部分はあったが、時間による妥協をせずに納得するまで作りこめた」と語るものの、「持続は無理。制作費1000万のうち、自腹で700万を出し、4年間かけて作ったのだが、700万という金額は下手したら年収の2年分に当たる。例えば、制作費100万の作品を半年で完成させるやり方もあると思うが、持続可能な少ない予算では人の心に響くもの、本当に撮りたいものを作るのは難しい」としている。内田監督も「圧倒的な利点は時間。何かに追われることがなく、自分たちで時間をコントロールして、納得いくまで追求できたのが大きい」とするものの、「持続はほぼ不可能。毎回、毎回、続けていくのは本当に苦しい。それに対する助成金制度があると僕らも生活していく上で楽になる」と語った。
芸術と商品の狭間で
彼らは自主映画そしてインディペンデント映画をどう捉えているのか。庭月野監督は「僕の中ではインディペンデント映画と自主映画は違い、インディペンデント映画は多少、商業要素があってもそう呼べるが、自主映画になると自腹映画、ボランティアの映画だと思う。自腹映画とは言え、本当はキャストにもスタッフにも相応のお金は払うべきであるが、払うことができないという葛藤のもとやっている」と語り、内田監督は「商品か芸術か。芸術であっても、人さまにお金をもらって観てもらう以上は商品でもあると思う。また、芸術も娯楽だと思っている。映画というものは芸術でもありたいし、商品としてもやっていきたい。その葛藤で揺れている」と話し、「より芸術性の強いものが、インディペンデント映画として定義されることになるのではないか」とした。深田監督は「すぐには答えの出ない抽象的な概念」としながらも、インドネシアのプロデューサー、メイスク・タウリシア氏から聞いた「お金の出処というよりは、監督あるいはプロデューサーが創作の独立性を保っていること」という概念がしっくりするとしている。また、「例えプロデューサーと良好な関係を築いたとしても、映画は集団創作である以上、監督は完全に自由なわけではない。しかし、監督の持つ自由の領域を少しでも広げていくためにどうやってお金を集めていくかを考えることはできる」と述べた。

「そういった自主映画、自腹による映画は持続できないのなら、どうしたいと思っているのか」第一部の最後、土屋監督が両監督に尋ねた。庭月野監督は「芸術性を残しつつ、商品価値を高められれば。企業から出資をしてもらいつつ、自由な範囲を確保することを考え続けている。独立映画ファンにも、大手映画ファンにも、どちらの琴線にも触れる映画、常に中間のところを捜し続けている」とし、内田監督は「僕らのように必死で働いて映画を作っている人たちを、援助してくれる人がいることがベスト。その都度、探していくしかないと思う」と答えた。
第二部「アジアの映画監督から」
総合司会:土屋豊 ゲスト:エレン・キム 五十嵐耕平 聞き手:市山尚三
国際共同製作を通して
五十嵐監督は東京造形大学在学中に手掛けた『夜来風雨の声』(2008)がシネマ・デジタル・ソウル映画祭で受賞。その後、東京藝術大学院映像研究科に進み、修了作品『息を殺して』(2014)がロカルノ映画祭新鋭監督部門に選ばれる。そこでフランスのダミアン・マニヴェル監督に出会う。意気投合した二人は最新作『泳ぎすぎた夜』(2017)を共同で監督することに至る。ヴェネチア映画祭、今回の東京フィルメックスに選ばれている本作は、雪の青森を舞台としている。その製作の成り立ちについて、フィルメックスのプログラム・ディレクターである市山さんが聞き出していった。
『泳ぎすぎた夜』は「ある男の子が雪の中を歩いて行く1日」というミニマムな映画だが、撮影に1ヶ月半もかけたという。もともと、日本で撮ることを言い出したのはダミアンの方である。資金面ではダミアンたちの会社が出資をし、配給及び制作会社としてシラク(諏訪敦彦監督の『ライオンは今夜死ぬ』も手掛けている)が入り、それらの資金に加えて両監督もお金を出すことで成り立っている。「ダミアンが日本人の監督と日本で子供の映画を撮りたいと言っている」それだけで、シラクのプロデューサー、トマ・オルドノ氏が動いてくれる。当初はちゃんとしたシノプシスもプレゼン資料もなく、企画意図のみであった。トマ・オルドノ氏とダミアンの関係、氏の人間性によって成り立っているらしい。その後、プレゼン資料をいろいろ作ったものの、撮影に対してはシンプルなプロットのみで「事前に詳細を決めずに臨んだ」と言う。
五十嵐監督はフランスのポストプロダクションにおいて、日本との意識の違いを感じている。日本よりもポスプロの比重が大きく、クオリティの高いスタジオも使いながら編集に5ヶ月もかけており、それによって監督自身が知らなかったものが見えてきて、「可能性が提示された」と語っている。市山さんは海外の監督と話していると、ポスプロの期間を長く設けていることをよく聞くそうだ。「日本はいかに短くやっているかということを常に感じる」と述べた。

韓国におけるインディペンデント映画
韓国のプロデューサー、エレン・キムさんは富川国際ファンタスティック映画祭のプログラマーであり、本年度フィルメックスの審査員も務めている。「韓国では予算、芸術性、配給の広がりといった様々な観点によってインディペンデント映画の定義がなされている」と話し、商業的に大ヒットしたものや、制作費が高い作品も含まれるらしい。制作費1,000万ドルと言われるナ・ホンジンの『哀しき獣』や、あるいはポン・ジュノのように時間とお金を操作し、作家としての自由度を広げる力を持った監督の作品がそれにあてはまる。そういった例外はあるものの、基本的にはインディペンデント映画は低予算で芸術性の高いものを目指すものであり、「韓国ではそのコミュニティがとても強い」と言う。現在のムン・ジェイン政権ではKOFIC(コフィック・韓国映画振興委員会)のメンバーが刷新され、プロデューサー、監督、脚本家、撮影監督、インディペンデント映画、女性映画、それぞれの団体の人たちがバランス良く並び、今後、映画に対する公的資金の在り方が向上することを期待されている。過去にはKOFICにおいても、インディペンデント映画の定義が混在していた時期もあり、助成金制度も紆余曲折を経てきている。韓国の助成金制度は製作、企画、そして、配給にまで及び、さらにインディペンデント映画を上映する劇場をサポートする構想まであるらしい。
エレンさんはインディペンデントというのは「非常に実践的なところから考えなければならない」としている。韓国の特徴として、政府やKOFICに影響を及ぼす強いアクティビズムを挙げ、「結局のところ、インディペンデントとは精神、価値観のことで、それを掲げようとする人たちが行動し、初めてインディペンデント映画は成立するのではないか」と述べた。また、「オープンであることが大事」とし、インディペンデントのみならず、韓国映画界全体の動きとして、配給から上映までの全てを独占しようとしている会社に対抗し、アンチトラスト法というのを実現させようとしており、「映画業界全体で力を合わせようとしているところがある」と語った。

どのような作品を望むのか
一口にインディペンデント映画と言っても様々である。フィルメックスにおいてはどのような観点で作品を選んでいるのか。市山さんは五十嵐監督の作品を引き合いにしながら次のように語っている。「応募作は自主映画がかなり多いと思われる。いわゆる商業映画のコピーのような作品がけっこうあって、観ているとイライラしてきて、もっとパンチのあるものを観たいと思ったりもする。そんな時、今回の五十嵐さんの作品はある意味、衝撃的で、是非、上映したいと思った。海外の作品にはそういうものがけっこうあり、それらに対抗して選ぶ日本映画は、ある程度よくできていて商業性のあるものより、そこから離れていて、『何かすごいものを観た』という印象を受けるものになる。そういったことが価値基準になっていると思う」
五十嵐監督は「自分にとってのインディペンデント映画は」という土屋監督からの問いに次のように答えている。「作った映画自体が自分の実人生と切り離せないものであること。『こういう風に生きていきたい』という態度の中で、自分が思っている映画が作れるということがいちばん大事」これには多くの共感が集まったようである。

第三部「全員でディスカッション」
第一部、第二部の登壇者全員
韓国と日本の現状を踏まえて
第二部を受けて深田監督は「韓国に比べて日本の文化予算は半分しかない。国家予算の規模を考えると4分の一。そういった状況の違いがある中で、日本にはない韓国の充実した助成金制度が行政から一方的に与えられたものではなく、映画人の運動の結果によるものだということにすごく勇気づけられる」「五十嵐さんの実人生につながっているという定義はいい言葉」とし、インディペンデント映画とその助成金について「どういった映画に助成金が下りるべきか、インディペンデント映画とは何かというと、それは作家の視点がちゃんと織り込まれている映画だと思っている。いわゆる芸術を作る価値や意義は時代によっても違うが、それは大昔から絶えずあるもの。なぜ、今、芸術をサポートする必要があるのかというと、視点、思想、価値観の多様性をちゃんと社会に顕在化させることが民主主義にとってすごく重要だから」と述べた。
ここで、土屋監督から以前の鍋講座で教えられた、韓国における多様性映画の質的な側面による定義が伝えられる。「1.芸術性や作家性を大事にする映画、2.映画のスタイルが革新的であり、美学的価値がある映画、3.複雑なテーマを扱い、大衆が理解しがたい映画、4,商業映画の外で、文化的、社会的、政治的イシューを扱う映画、5.他国の文化や社会に対する理解に役立つ映画」深田監督は「この5つは今、聞いても震える」としながらも、「日本だと政治性があることによって、公共の助成にアクセスできなくなる状況がある」「韓国そしてフランス、どの国も助成金を適切なものにし、多様性を守るために何とかルール決めようとしている。エレンさんの話を聞いて、この辺が日本の映画に限らず、助成金とかにおいて不足していたと感じる」と語った。
どんな映画なら支援したいのか
登壇者全員に土屋監督から「もし、手元に映画製作に使える5億円があったなら、どんな作品だったら支援をしたいか」という質問が出る。エレンさんは「カンヌ国際映画祭でカメラドールを獲るような映画」五十嵐監督は「自分では面白いとは思えないけど、『何かを確信しているのではないか』という映画にお金を出したい」庭月野監督は「自分がすごく面白いと思え、会社だと撮らせてもらえないような、大手がコンプライアンス的に避けそうな、攻めている企画に出したい」内田監督は「自分が生きてきて『本当にこの映画だけはどうしても今、作りたい』という熱意のある人に出したい」と答えた。
市山さんはフィルメックスが関わっている『タレンツ・トーキョー』映画人材育成プロジェクトの助成金プログラムの決め手について語った。「簡単に言うと、いちばん大きいのは『この映画が観てみたい』ということ。『何かわけがわからないけど面白いものができそうな気がする』ということ。逆に『すごくかっちりとできそうな気がするので出してみよう』ということもある。また、内田監督が言われた『今、これを撮らないといけない』ということ。例えば、フィリピンではドゥテルテ政権が麻薬犯を路上で殺すということをやっており、今回のフィルメックスで上映する『暗きは夜』はそのことを劇映画として撮った作品ですが、それをドキュメンタリーとして潜入して撮るという危ない企画に対して、『これは支援せざるを得ない』ということで決めることがある。切実に『撮りたい』ということが書類から滲み出ているようなものを支援する。インディペンデントの作家が撮ろうとしているものには、企画だけできて、脚本だけできて、映画自体はできないものもある。そういったものに対して、この助成金プログラムの100万が出ることによって、『何かを進めていく推進力になれば』と思っている。
深田監督は支援すべき映画について「作家の視点がちゃんと現れていること。そして、商業性が低いこと。インディペンデント映画と商業映画は対に思われることが多く、自分もついついそういう表現をすることもあるのだが、実際、商業性の「ない」映画はほとんど存在しないと思う。高いか低いかで考えなければならないと思う。助成金について言うと、どこからの助成金であるかということも関係してくる。経済産業省の助成金だと、当然、産業促進だから売れそうなものにお金を出すことになっている。日本ではそっちに傾きすぎていることが問題。文化への助成金はむしろ商業性の低いもの、作家性そして作品そのものに対してバックアップするべき」と述べた。
土屋監督は「ほぼ皆さんがおっしゃっている通り。自分が出さなくても、他の誰かが出しそうなものには出したくないと思う。驚きのある作品で、『このお金がなければ絶対に撮れないだろう』という作品を支援したい」と語った。

日本におけるプロデューサーの現状
質疑応答では来場者から「監督に限らず、プロデューサーが打算を超えた熱意を持ってやることも、インディペンデント映画の核心にあるのではないか」という意見が出る。これに対しては登壇者たちも同感し、話はプロデューサーの重要性に移っていく。深田監督は「欧米だとプロデューサーの存在がすごく大きい。特にフリーランスのプロデューサーは非常にクリエイティブ。やりたい企画を動かして、監督を選び、出資者というよりはクリエイターとして作品にどんどん口を出してくる。日本では大企業や大手スタジオのプロデューサーの存在があまりにも大き過ぎるがゆえに、多様性が損なわれることにもつながっている」とし、市山さんは「ヨーロッパにおけるフリーランスのプロデューサーは、助成金の申請が通ると、その証書を持って銀行でお金を借りることができるので、極端に言えば1銭も持ってなくてもプロデュースができる。日本だと会社に所属していないプロデューサーが助成金の証書を見せても、おそらく銀行は貸してくれないし、しかも、その助成金は映画が完成しないともらえない」と述べた。それを受けて庭月野監督は「日本におけるプロデューサーの不在がインディペンデント映画の不遇にもつながっているのではないか。自主映画は、監督がプロデューサーを兼任して進むことも多く、映画の活かし方、戦略的なことも疎かにしがちでは」とし、深田監督は「インディペンデントの場合、ある程度、監督自身がプロデューサー的な資質を持つことも必要だと思うが、日本の状況ではあまりにもフリーランスのプロデューサーが生きづらい。お金の回し方が難しく、私が一緒に仕事をしているフランスのプロデューサーは『日本では絶対自分はこの仕事はできない』と言っている」と述べた。
助成金はどうあるべきなのか
来場者からもうひとつ質問があった。「五十嵐監督のおっしゃった『インディペンデント映画は実人生と切り離せないもの』というのはいい言葉だが、助成金を得るための定義とした場合、行政は納得するのか。納税者は納得するのか」冒頭、土屋監督が挙げたこのシンポジウムの企画理由そのものである。助成金の審査員経験がある市山さんは「その問題は非常に大きい」とし、「文化庁の助成金は製作費が5,000万以上の作品、国際共同製作だと1億円以上の作品じゃないと応募できない。国民の税金から出ているお金なので、『広く見られるもの、全国で一斉に公開されるものでなければならない』という理屈があるらしい。いろいろ考えると疑わしいのだが。小さい映画であっても文化の多様性につながり、ある種の価値を生み出すし、また、国際映画祭においても五十嵐さんの今回の作品が、北野さん、是枝さんの作品と共にヴェネチアに選ばれているということは、小規模でも思い切った作風であることは海外評価されるためのひとつの手段だと思う。そこをサポートする助成金が必要。そういったことが理解されないと、文化庁がインディペンデント映画を助成することは難しいかもしれない。ただし、いいニュースもある。文化庁の予算案が通れば、製作費が1,500万以上の作品に対しても助成金が下りることになる」と話した。深田監督は「ある意味、日本の納税者に文化の価値をどう説明できるか次第」とし、個人的な考えとしながら、「結局は民主主義と結びついていると思っている。昔は単純な多数決だったが、これからはマイノリティの声も政策に反映させていくことが必要。そういった状況が成立するためには社会において多様な価値観、人それぞれの価値観がちゃんと活かされ見えることが重要であり、それが民主主義の最低条件でもある。そこにおける芸術、文化の果たす役割は非常に大きい。したがって、文化が抑圧されている国であればあるほど、民主主義の成熟度が低い。そのことはどの国を見ても明らか。だからこそ、個人の価値観、人生に結びついているものに助成金を出すべきではないか。日本にも政治的検閲がないわけではないけど、それよりも過度の市場原理が結果的に文化の多様性を抑圧している状況。」と述べた。
インディペンデント映画のために
内田監督は自身のような映画作りに対する想いを語った。「僕が話したような少人数での制作を続けていくことは難しいが、やる価値は絶対にある。熱意があれば続けていけると思う。PFFをセレクションメンバーとして見ているが、熱意のある作品を観ると震える。そういった作品をたくさん観て、たくさん震えたいということもある。」
土屋監督はシンポジウムをこう締めくくった。「韓国には『市民が前に出れば政治家が後からついて来る』という言葉がある。僕らは、この5,6年の間、深田さんが言ったような映画を作りつつ、製作、配給、劇場に関わる人たちが『もっともっとアクティブになると状況は変わっていく』と言い続けてきた。そして、これからもそのための活動を続けていく。」
『インディペンデント映画って何だ!? 』このタイトルに対する答えは少なからず見えてきたのかもしれない。しかし、世の中そして行政側に訴える「定義」という意味においてはある種のもどかしさがある。韓国のエレンさんが語ったように、インディペンデント映画という概念は、それに携わる人間の「行動」によって成立するものだと思う。我々は今後もその「行動」の先頭に立ち続けなければならないし、そうすることによって、近い将来、「定義」は自ずと確立され、道は開けるのではないだろうか。
(レポート:谷渕新吾)
※当日の記録動画