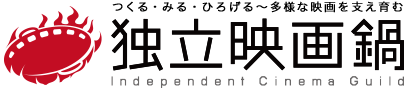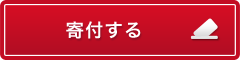レポート【鍋講座 vol.36】映画人よ、ラテンアメリカを見よ! ~これからの「持続可能」な独立映画製作を考える~
「ラテンアメリカ映画」と聞いて、具体的なイメージがすぐに浮かんでくる人は少ないだろう。これまで映画鍋でも、ヨーロッパやアジアの映画事情は何度も扱ってきたが、ラテンアメリカは取り上げたことがなかった。ラテンアメリカは日本にとって遠い存在なのか?決してそうではない。むしろ、日本の映画人が学ぶべき、大切なヒントがそこにはたくさんあることを、今回の講座の参加者は感じ取ったはずだ。そして、私たち映画鍋にとっても、これからの活動方針を考えるうえで、この鍋講座はとても重要なイベントであったことを先に記しておきたい。ラテンアメリカから日本へ、比嘉さんの率直なメッセージが響いた鍋講座を振り返る。

◆ゲスト:比嘉世津子
Action Inc.代表。1992年よりNHKスペイン国営テレビ(TVE)通訳。字幕、映像翻訳。スペイン、イタリア、ラテンアメリカの独立系作品を買付け国内配給。2015年、配給10周年として「ラテン!ラテン!ラテン!」のタイトルで配給作品16本を新宿K’s cinemaにて一挙上映。2016年、映画「エルネスト」の台本翻訳、キューバロケで阪本順治監督通訳。現在日本とラテンアメリカ諸国との対等な合作企画を進行中。
◆聞き手:植山英美
アーティクルフィルムズ代表。18年間を米国・ニューヨーク市で過ごし、2012年の帰国後、宣伝、プロデューサー、ライター、国際セールスなど多岐に渡り映画に関わる。日本のインディペンデント映画を海外に紹介するほか、合作製作作品3本進行中。
ラテンアメリカの映画事情
まずは、ラテンアメリカ映画の状況をまとめよう。ラテンアメリカと一口にいっても、北から南まで33の国がある。各国の映画産業の規模はバラバラで、大きな映画産業を持つメキシコやアルゼンチンといった国もあれば、パラグアイのようにほとんど産業として成り立っていない国もあるので、乱暴にまとめることは禁物だ。しかし、比嘉さんのお話からは、規模の違いはあれど、ラテンアメリカの多くの国々で共通している映画事情がいくつかあることを伺える。
まずは、各国の映画協会の存在だ。アルゼンチンのINCAAや、メキシコのIMCINEが有名どころ。ラテンアメリカの多くの国々では、映画協会が自国の映画文化を守ろうと奮闘している。世界の映画祭にむけて自国の作品をプッシュしたり、インディペンデント映画を保護する政策提言を行ったり、自前の映画館でアート系の作品を積極的に上映したりと、様々な試みを行っているようだ。
こうした映画協会の働きは、アメリカ合衆国のお膝元、強大なハリウッド映画から自分たちの映画を守るため、という側面もあるだろうが、ラテンアメリカの歴史と密接に関わっている点も興味深い。この地域では、軍事政権の暗い時代を経験した国が少なくない。たとえば、アルゼンチンでは、多数の犠牲者や行方不明者を出した軍事独裁時代に、映画を自由に作ることができなかった。いつまた独裁政権によって、表現の自由が脅かされるかわからない。そんな危機感をもって、各国の映画協会は映画文化を守ろうと、積極的に動いている。
このような歴史的経緯は、「インディペンデント映画」を定義づけるうえで有効なものだろう。激しい政変の中で闘ってきたアジアの国々の映画のように、権力に対する「カウンター」として、「インディペンデント映画」を捉える文化がラテンアメリカにも根付いている。
しかし、日本で今「インディペンデント映画」と言うとき、上に書いた歴史的、カウンター的な側面が意識されることが現状ではあまりないことは、これまでの映画鍋のイベントでも確認してきた。それよりは、より経済的、実務的な面で、大手に頼らず、自分たちの手で、自分たちの作りたいものを作る、という意識が強いはずだ。そのようにインディペンデント映画を作る、そして、作り続けるためにも、ラテンアメリカの映画人たちは大いに参考になると比嘉さんは語る。

自立しながら、連帯する
ラテンアメリカの映画作家は、自らの映画作りについて、はっきりしたヴィジョンを持っている。なぜこの映画を自分が撮らなければならないのか、といった熱い思いを各自が持っている。だから惹き付けられてしまう、と比嘉さんは語る。そして、情熱だけではなく、彼らは自らのキャリアについての冷静な見通しも持っている。一本目の作品は、しっかりと練ったアイデアで短編を作り、それを映画祭へ持っていく監督が多いそうだ。そうすれば次の作品につながりやすい。もともとラテンアメリカの映画産業はそこまで巨大ではなく、さらにインディペンデントとなると使えるお金は限られる。だからこそ、彼らは自らの将来を見据えて、知恵を振り絞る。
助成金についても、有名なフランスのものを一方的に信頼するのではなく、その内容をよく吟味している。助成金のなかには、ポストプロダクションや宣伝費によって、フランスにお金を落とすような仕組みになっているものもあるので、自分たちの利益にならないと考えれば、条件の合う、他の国の助成金を探すことも彼らは厭わない。
ラテンアメリカの監督たちは、自立した監督たちだ。自分の撮りたいものへのこだわりと、それを広く世界に届け、次の作品を撮れる環境をつくっていくための、自分なりの考えをもっている。しかし、いくら自立していても、映画作りは独りでは続けていくのが難しい。だからこそ、彼らは連帯し、お互いの映画作りを助け合っている。最も成功した例が、近年ハリウッドでの活躍著しい、ギジェルモ・デル・トロ、アルフォンソ・クアロン、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥのメキシコ3人組みだ。彼らは、自らの作品を監督する傍ら、プロデューサーとして仲間の映画の手伝いや助言を欠かさず行っている。彼らの他にも、チリのパブロ・ララインなどラテンアメリカの映画人には、ヨーロッパやハリウッドで成功したあと、自国へ帰って国の映画の発展に協力する人が多い。
彼らの自立と連帯の姿勢は、着実な成果となって表れている。ハリウッドは、独自のアイデアで脚本を書け、映画を撮れる彼らに注目しているし、各地の映画祭でラテンアメリカ映画が躍動している。大きな産業の中でも、彼らは独自の存在感を発揮している。
「独立映画」とは、その名の通り、独立した映画だ。大きな資本や権力に頼りきることなく、映画作家が、確固たるヴィジョンをもって、自立した映画製作を行うことだ。しかし、それは独りになって映画を作るという意味ではない。志を共にする人たちがお互いに助け合うことが、映画を作り続けるためには必要だろう。自立しながら、連帯する。そうしたインディペンデント映画の精神をよく表しているのが、ラテンアメリカ映画なのではないだろうか。

日本映画のこれから
ここまでの話を踏まえて、当日比嘉さんが熱く語っていた日本映画の状況に踏み込もう。まず、比嘉さんが何度も言うのは、日本人はもっと自分たちのプレゼンスを示せ、ということだった。たとえば、自分たちの日本映画を海外で売るときに、「買ってもらえるから」とほっとして安売りするのではなく、もっと交渉しなければならない。または、撮影所が消え、会社に頼ることができない独立系の映画人は、自分たちでお金を集める方法を考え、世界にアピールしていかなければならない。
これは、映画人に対して、「自立してほしい」というメッセージだ。日本のクラウドファンディングの現状について、日本で成功した作品を海外で上映するためのお金を集めるのはおかしいと比嘉さんは指摘した。クラウドファンディングは本来、まだ価値の定まっていない企画に、将来的な期待をかけて投資するものだからだ。ある程度成功した作品を海外配給するなら、人の善意に頼るのではなく、その配給会社が責任をもって行うべきなのではないか。自分のできることは覚悟を持って引き受ける、そしてできないことはできないとはっきりと言い、他のツテを紹介する。このような自立した姿勢が今求められている。
しかし、いくら映画監督が自立していても、独りでお金を集めたり、海外と交渉したりするのはつらいし大変。だから、仲間が必要だ。「監督を孤独にさせない。独立だからこそ、集まって楽しんでできるように、監督が相談できる人、監督の盾となって交渉を行うプロデューサーのような人がすごく大切」と比嘉さんは言う。今、監督をしっかり支えられるプロデューサーや助監督の人材が不足しているのだ。そういったところから経験を積んで、後のキャリアに生かしたり、またはラテンアメリカの例に倣って、成功した日本の監督が、若手の映画をプロデュースするなどできれば、もっと映画人の協力の輪は広がるかもしれない。
仲間を集めるには、日本にこだわらず海外に目を向けてもいいだろう。現状でも、日本で製作されている益々増えていて飽和状態にあるのだから、視点を変えて、海外を狙った企画を考えるのも戦略の一つだ。比嘉さんの話では、世界の映画業界人にむけた、脚本のプラットフォームのようなものもいくつかあるとのことなので、そういった場所に企画を投げて、気の合う人を見つけるのも有効だ。
最近、中国はメキシコと、韓国はアルゼンチンと、映画製作における二国間協定を結んだらしい。こういった協定があれば、ビザのスムーズな発行や税の優遇など、映画製作における様々な障害が取り払われる。日本にも中国との間で協定を結ぶ動きがあるようだ。こういった制度が整っていけば、世界の映画人と交流が生まれ、日本映画は活性化するはずだ。または、アルゼンチンやメキシコが映画教育を重視しているように(メキシコの国立フィルムセンター「シネテカ」は10スクリーンとおしゃれなカフェを備えていて、積極的にイベントも行っている。デートに使えるくらい、誰もが気軽に行ける場所だ)、日本でも、将来の映画を支える観客の育成のため、少し難しい映画でも気軽に観られるような環境をつくっていかなければならない。
自分たちのプレゼンスを高めながら、共に映画をつくる仲間をつくること。そのために、そういった仲間が増えて、集えるような環境を整えること。これが、これから日本で独立映画を作り続けていくために必要なことだろう。イベント中、比嘉さんは何度も「映画鍋にギルドとしての役割を期待している」と言った。映画鍋は、日本の独立系映画人が集まることのできるギルドとして、またそうした映画人を助けるために、積極的に動いていく大きな盾となって、世間に向かって働きかけるべきだろう。「現状に不満はたくさんあるが、文句を言うのではなく、できることをやっていくことが必要です」と比嘉さんは言う。大切にしたい言葉だ。
(文責:新谷和輝)