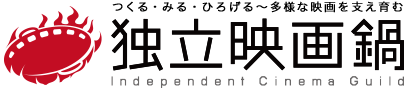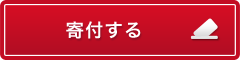【鍋講座vol.23】「文化は助成金とどう向き合うか ~支出する側の論理と受け取る側の論理」レポート
【登壇者】太下 義之:公益社団法人日展理事、公益社団法人企業メセナ協議会監事、公益財団法人静岡県舞台芸術センター評議員、文化審議会文化政策部会委員、東京芸術文化評議会委員、大阪府・大阪市特別参与、沖縄版アーツカウンシル評議員など、文化政策関連の委員を多数兼務。
小川 勝広:京都造形芸術大学・映画学科/専任講師。プロデュース作『ブタがいた教室』『乱暴と待機』『道~白磁の人~』など。
土屋 豊:独立映画鍋共同代表。『タリウム少女の毒殺日記』監督、プロデュース作『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(監督:太田信吾)など。
【ファシリテーター】伊達 浩太朗:独立映画鍋理事。プロデュース作『サウダーヂ』(監督・富田克也)『解放区』(監督・太田信吾)など。
【開催】2015年5月16日(土)15:00 〜@下北沢アレイホール

鍋講座23回目は、「文化は助成金とどう向き合うかー支援する側の論理と受け取る側の論理—」をテーマに開催されました。まず『解放区』のプロデューサーでもある伊達さんから、今回の講座の主旨説明として、映画鍋会員の太田信吾監督の映画『解放区』がその製作過程で大阪映像文化振興事業実行委員会からの助成金を返還するという事態になった件を踏まえ、そもそもなぜ行政は文化助成を行うのかという基本的な部分を学ぶために開催した、というお話がありました。
まずは行政の文化政策などに造詣の深い、太下さんの講義から始まりました。以下、そのお話の内容をまとめます。
1.映画支援の現状
2.支援する側の論理:なぜ文化を支援するのか
文化経済学の観点で国が文化芸術に支援する理由は主に7つで、なぜサポートされなければならない理由を掘り下げると①文化遺産説:劇場や美術館に行かない人々にも、文化遺産として後世に残したいと望まれるもの継承②地域アイデンティティ説:優れた芸術の存在が国民に威信をもたらすことがある③地域経済波及説:『ローマの休日』のように、芸術の存在が理由で観光客や有能な労働者を集めやすい便益の発生④一般教養説:芸術という教養が社会全体に利益をもたらすことがあるが、利益が発生しないので公共の支援が必要⑤社会批判機能:社会批判機能としての社会への便益(ドキュメンタリー映画が含まれる)⑥イノベーション説:文化芸術を通じた社会実験の成果が、たとえ失敗したとしても社会に便益をもたらす可能性がある⑦オプション価値説:現時点の評価からはわからない将来性への公共の支援、などがあげられるそうです。文化と芸術は準公共財的特徴があり、私的財と公共財の中間にあり、市場のメカニズムに任せておくと十分な供給がされない可能性から、公共がサポートするという理屈です。
3.支援する側と支援される側との関係性:アームズ・レングス
4.表現の自由と不自由(検閲・規制)について
近・現代史で最も大きい検閲といえば、ナチス・ドイツが「退廃芸術」という名の元で近代美術に行った弾圧で、1933年5月10日に行われた「非ドイツ的著作物の焚刑」をモチーフにしたミハ・ウルマンの『図書館—1933年5月10日焚書記念碑』が今日のベルリン広場に設置されていることを挙げられました。

検閲にあったものが色々紹介されました。
【書籍】:
『ボヴァリー夫人』(1956)、『北回帰線』(1934)、『ライ麦畑でつかまえて』(1951)、『華氏451度』(1953)、『ロリータ』(1955)、『裸のランチ』(1959)、『走れウサギ』(1960)、『リタ・ヘイワースの背信』(1968)、反戦的な主張が米国では引っかかるのか、『スローターハウス5』(1969)、『ちびくろ・さんぼ』(1899)、『悪魔の詩』(1988)、『断筆宣言』(1993)など。文学の歴史は検閲の歴史と言えるようです。
【映画】:『米国女優フラー嬢胡蝶舞』(1897)、日本で初めて上映禁止になった『仏国大革命 ルイ十六世の末路』(1908)、『フリークス』(1932)、『風とともに去りぬ』(1939)、永遠に短縮版しかなくなった『姿三四郎』(1943)、『太陽の季節』(1956)、『恋人たち』(1958)、『ラストタンゴ・イン・パリ』(1972)、『ソドムの市』(1975)、『愛のコリーダ』(1976)、『ライフ・オブ・ブライアン』(1979)など。
【演劇】: 歌舞伎にも検閲の歴史があり、遊女歌舞伎禁止(1629)、若衆歌舞伎禁止、実在の人物名使用の禁止(1644)、狂言綺語(作り話)禁止(1872)、GHQにより「仇討ち」演目上演禁止など。大衆演劇の事前検閲としてルネサンス演劇(16C〜17C前半)、『春の目覚め』(1891)、『ゴドーを待ちながら』(1952)、ジャン=ポール・サルトル『出口なし』(1945)は、平田オリザがロボットによる上演を企画し、遺族の反対により中止になったそうです。
【アート】: リチャード・セラ『傾いた弧』論争(1981)、富山県立近代美術館天皇コラージュ事件(1986)、ロバート・メイプルソープ回顧展(1990)は政府の支援のあり方について大きな問題になりました。レスリー・キー(2013)、光州ビエンナーレ(2014)、『表現の不自由展』(2015)など。
【マンガ・アニメ】: 『アシュラ』(1970-71)、『ブラック・ジャック』の一部封印(1977)、『境界のないセカイ』連載中止(2015)、『TERRAFORMARS』(2014)など。
【音楽】: ソ連時代のロックのブラック・リスト(1985)、タリバンによる音楽の禁止(1996-2001)。逆に、いい例として、人種差別の激しい時代に登場した、黒人白人音楽の融合した音楽・エルヴィス・プレスリーが登場し(1956)、ロックンロールが生まれた例があります。圧力や規制が、新しい文化を生む原動力になることは容易に想像出来ますよね。
5.表現の不自由(検閲、規制)の本質的な問題
日本国憲法21条に、「1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と、いわゆる表現の自由・言論の自由の日本における根拠条文として保障されています。
いくつかの問題提起
ここで、幾つかの問題提起が。①表現の自由は「絶対善」なのか? 例えば「ヘイト・スピーチ」やシャルリー・エブド誌のJe suis Charlie(私はシャルリー)などは? ②検閲は「絶対悪」なのか? 例えば、歌舞伎、シェイクスピア、ロックの誕生のように、表現の不自由が副産物として文化の多様性をもたらすかも知れません。③誰(何)が検閲をもたらすのか? 権力者による一方的な表現の規制だけでなく、近年は映倫のような表現者自身によるものもあります。④「検閲」はいつまで続くのか? 未来永劫、新しい検閲は出現します。インターネット規制に不完全な部分を設けるべきだというローレンス・レッシグ著の『CODE-インターネットの合法・違法・プライバシー』(2001)で、インターネット規制について分析されています。
今あらためてケインズに学ぶ事
第二次大戦前後のイギリスでは、政府は文化支援をすべきでない論調が主流だった中、ケインズは「大衆は文化を求めている」と新しい文化の公共性を見出し、アーツ・カウンシルの設立に尽力しました。芸術や文化が持つ社会における大きな公共性にケインズが注目したことが大事なことで、新しい公共性について作り手側が考える必要があるのではないか。今人気があるものは私財としてマーケットで回していけばいいだけで、それがなくても表現することで大きな公共性があることを見出していくことが、公共からの支援を受ける道であり、また、自由と規制に立ち向かう正しい近道になるのではないか、と語り、太下さんの講義は終了しました。

⚫️ディスカッション
ディスカッションでは、引き続き太下さん、助成を受けた経験が豊富な小川さん、『解放区』の問題で映画鍋の一員として話し合いに参加した土屋さん・伊達さんの4人で、行政から支援を受け映画を製作していく上での問題点や配慮、行政のあり方などを語り合いました。
伊達さんは『解放区』の問題では、行政による検閲に見えるが、実質は「自主規制」に近かったと言います。土屋さんの『解放区』問題の経緯説明によると、まずCO2(シネアストオーガニゼーション・大阪)の助成金企画に企画書を送付後、大阪映像文化振興事業実行委員会から助成金が下りた後、撮影・編集と進み、仮編集が仕上がった時点で、大阪映像文化振興事業実行委員会(以降、実行委員会)から、「人権に対する配慮不足」というのが主な理由で削除要求があり、最終的に太田監督が「助成も上映もしなくていい」となったそうです。土屋さんは、大阪市の職員も含まれる実行委員会のメンバー構成や意思決定の仕組みに問題を感じたそうです。太下さんは、大学は学問と研究の自由が保証されており、文化の分野でも大学の教授会(専門家)で運営されているような独立機関があるべきだ、とケインズが考えていたことをあげました。しかし、大学の学問研究分野においては社会的認知されやすいのに対し、文化の分野では、アーティストやアーティストを支援する専門家という認定をするのが難しい状況の中で、お金を出す側が安心出来る組織形態を作るのが困難。行政がお金を出す時には目的があり、そこにマイナスの要素があると、お金を出す上で権利を持ちたいというのが人情。普通に考えると、「アームズ・レングス」が、理想・理念以上に成り立つことは決してないのだろう、と感じていると話されました。

多くの人たちから注目浴びるエンターテイメントや文化・芸術の分野では、逆に携わる人間たちが自主規制してしまうのが何となく見えるけど、どうか? という伊達さんからの質問に対して、小川さんは、「助成をする側とは、『表現の自由』からのアプローチで解決可能な問題や、現場的なコミュニケーションからアプローチして解決可能な問題など、色々なアプローチがあり、現場的な一般論で言うと、助成をする側はお金を出す以上は色々な考え方があるので、助成を受ける側は、その都度ちゃんと情報開示をしながら、お互いコミュニケーションを密にしていけば、基本的には様々な問題は解決可能。また、担当者の立場、行政側の立場もあることを考慮し、そこをうまく立ち振る舞い出来るように持っていく配慮も、助成を受ける側には必要で、例えば、シナリオで判断すると言われていても、シナリオ+わかりやすい資料を持って行くとか、ビジュアルで示すとか、とにかく相手に100%わかってもらえる資料を、助成を受ける側から出していくことが必要」と指摘されました。
作り手の覚悟についても話が及びました。『解放区』では、そもそも釜ヶ崎を主な舞台に撮るというシナリオを提出して許可が下りたのですが、それを大阪市の税金で描くことに対し、製作側がどれだけきちんと考えていたか、また、それを選んだCO2側も、市への理論武装や戦略が少し足りなかったのではないか、と言う土屋さん。
小川さんも、大阪にとっても非常にセンシティブな場所である釜ヶ崎を映画にすることに、どれくらいの覚悟があったのだろうか、疑問点を指摘しました。
伊達さんは、作り手の決意や行政への丁寧な説明も必要であろうが、日本では助成金(税金)を出す行政サイドも確固とした審査制度・審査基準がなく、実行委員会に選ばれた人も大変だから変なことになりやすい。だから小川さんの言うように、連絡を密に構築することも大事だと語りました。
欧米の一部の国のように、国家試験や資格の制度やシステムが、映画・芸術分野で必要ないのか、という小川さんに、太下さんは、「理論的にはありえる。日本でよくフランスの国家予算の8%のように、多額の文化予算をつけるべきだと言われるが、フランスには文化エリートが存在する。日本がそのように絶対的な文化エリートを雇用する社会になれるのか、ということです」。フランス以外の国ではどうかと訊くと、小川さんがポーランドの国立の映画大学を視察した時に、俳優でもスタッフでも、国家試験のような制度をパスすれば、仕事が無い期間は、政府から一定の生活費の補助を受ける事ができるシステムがある話をされました。

⚫️質問コーナー
会場1:行政側が、立場上とんがった企画を避ける傾向にあると感じますか? 政治に批判的な企画が、以前は大丈夫だったのに狭まった印象などはありますか?
伊達:『解放区』の問題についていうならば、政治状況の変化という感はない。行政の現場担当者が世間の批判を気にせざるを得ないなか起こった、一般的な問題に思える。しっかり理論武装した専門家集団なら世間に反論も出来るだろうが、現実には公務員が唐突に人事異動で担当者として矢面にさらされる。事実上、官僚組織が担当者を守ってくれない。『解放区』プロデューサーである私が言うのもへんだが、担当した公務員は自分で自分を守らなければならず、これでは保守的になるだろう。世間やネットに振り回され、担当した公務員が場当たり的に右往左往する。作り手の側も、どこに許可をもらい、トラブルになった時に誰が解決するのかわからない。こういう状況だという印象。
土屋:2003年に山形国際ドキュメンタリー映画祭関係(国民文化祭)のドキュメンタリー制作ワークショップの講師の一人を任され、事前にあった講師紹介の上映イベントの時に深く考えずに靖国神社で無許可で天皇の戦争責任について聞いたインタビュー作品を上映したいと言ったら、ちょっと問題になったみたいですが、その時は結局上映出来た。ここ数年で検閲や自主規制が変に強く働いていると感じるので、今だったらどうなっていただろう? と思う。
太下:先ほどから文化行政の成熟度の低さを指摘されていましたが、仕事柄、地方行政の担当者と接する機会が多く、結構な確率で就任挨拶の時に「私は文化のことがよくわからないので、どうぞ宜しくお願いします」と言われる。これを福祉・医療の現場で置き換えたら、こんな間抜けな挨拶はあり得ない。文化についての行政の認識はその程度だと感じる一方で、ここ10年の傾向として、社会全体に批判に対する恐怖や不信が自己規制を生んでいる。それはインターネットが急激に普及する中、人間の汚いところが可視化され、誰もが自由に意見を発表できるようになったことにも関係している。色々過激な主張や批判も出てくるし、みんな護身したい。そんな中で表現者たちはつくる、そんな非常に大変な時代がきちゃった、ということです。
小川:インターネットが出現し、悪口や中傷が市民権を得ていることに対し、理不尽な発言に対して、理不尽だよ、と個人同士なら言えるけど、それが出来ない組織があることを、お金を出してもらうこちら側が考え始めなければいけないケースも増えてきた。こっち側からすると「そんなこと気にしなければいい」と思っても、大きな組織だとそういうわけにもいかない。
会場1:60年代の大島渚さんのような作品のように、ある種政治性の強い内容のものを作りたい時、商業性が高くないからこそ、助成の必要性があると思うが、行政が意識せねばならないこともわかる。突破口はないのか?
小川:内容がタブーを破るもの、面白いものならやり方によってはビジネスになる。そこは助成金に頼るとか、コンプライアンスを気にするとか、ではない製作方法が良いと思います。
会場2:スクリーン数はシネコンに限定され、独立映画の上映環境は良くない。文化庁、経産省は現在の映画業界についてどう考えている?
太下:今までの映画は産業分野のひとつで、作られたものを海外に出すとか、いかに稼ぐかがゴールの支援だった。でも、ここ直近の話、製作本数が驚異的に増え、これに対応する政策はなく、これからだろう。一方で、映画評論家の寺脇さんが文化部長になったことで文化庁から文化施策という観点で映画の支援をし始めている。だから本当は、文化庁的支援・経産省的支援の連携が必要。総務省は旧自治省と旧郵政省の合併した省で、通信と放送、コンテンツの流通を所管している。現代は全てが映画館でかからないがインターネットなどを通じて、人類はかつてないほど映像を観ている。これら全部を横断しないことには、これからの映像政策は出来ないだろうが、具体的な動きは、まだない。

土屋さんは講座の最後に感想として、文化を担当する行政の人間が、「文化がわからないんです」と就任挨拶するのは大問題で、文化エリートや、芸術文化が好き・守りたいという人に行政側で担当して頂き、制作側がそういう人たちと戦略を立てていくイメージだと非常にわかりやすい、とおっしゃっていたのは非常に共感しました。小川さんのアドバイスされていた助成を受ける側から、助成する側にすべきことの数々は、どれも非常に真っ当なご意見だと思いました。アートの分野では、日本でも文化庁の予算もつき、色々なキュレーターもおり、熱心で、層が厚い印象を個人的に持っていますが、映画は明らかに商業主義から製作されるものが多く、同時にインディペンデントで製作する人も多くいて、そういう人々にはお金がない。この多様性をもう少し助成を必要とする側から国に訴え、文化庁的支援・経産省的支援の連携してもらうなど、どんな支援を必要としているか伝えていくことの重要性を感じました。そのためには、欧州の様に文化エリートが必要かなど、明確なビジョンが必要だと思います。今後も考えていくべきテーマだと思いました。
(文責:山岡瑞子)