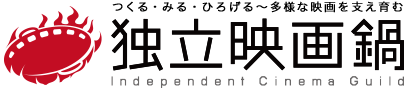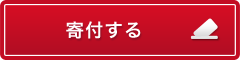【鍋講座vol.4 法律編①】 映像の著作権とは 「グッバイ・キャロル事件」から考える レポート
2012年11月15日 於下北沢アレイホール 【ゲスト】末吉亙(すえよし わたる)弁護士

独立映画鍋が定期的に開催している映画に纏わる勉強会「鍋講座」。11月には「法律編」と題して、知的財産権などを専門に活動されている末吉亙弁護士をお招きし、下北沢アレイホールで開催された。鍋講座vol4法律編①概要
会場は静かな熱気に満ちて、議題が議題であるためか、切実な関心を持って参加する映画・映像関係者が多く見られたようだ。
末吉弁護士が、映画の著作権について考えるうえでのひとつのサンプルとして提示したのが、「グッバイ・キャロル事件」だ。矢沢永吉がメンバーとして参加するロックバンド「キャロル」。その解散ライブの様子を記録したドキュメンタリー映画「グッバイ・キャロル」は、昭和50年の撮影時から28年を経て、DVD化に際し、映像監督とレコード会社の間で、その著作権の帰属を巡り争われることになった。末吉氏は、裁判に馴染みのない一般の人間にはやや難解な事件の概要を噛み砕き親しみやすい言葉で説明しながら、映画・映像の著作権の難しさを解き明かしていった。
●「著作者」≠「著作権者」?
著作権法においては、第十六条において、映画の「著作者」は「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」とある。つまり、今回の事例では、作品の構成を練り、撮影の指示から編集まで担当した監督が「著作者」ということになる。しかし一方で、著作権法第二十九条では、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する」としている。つまり、「著作者」と「著作権者」が別々に規定されているのだ。
末吉氏が語るには、この二つがわざわざ条文で区別されているのは、他の分野の著作物ではあまり例のない、映画の特殊事情であるようだ。映画は、例えば絵画やマンガ、文学と比べ、より集団創作の色合いが濃く、特定の個人に権利を集約させにくい。そのため、このようなややこしい規定が設けられているのである。
「グッバイ・キャロル事件」の場合、撮影当時、監督が「著作者」、監督の経営していた映像制作会社が「著作権者」ということに、一応なる。そうして撮られたドキュメンタリー映画「グッバイ・キャロル」が、ビデオ、DVDと二次利用されていく過程で、権利の譲渡があったのかどうかが重要な争点となった。結果判決としては、「著作権者」(=制作会社)の「複製権」はソフト化に際し譲渡されていたものとして制作会社の請求を棄却、「著作者」(=監督)の「著作者人格権」については侵害されたものと認められた。「著作者人格権」とは、その著作物の内容を他者に無断で改変させない「同一性保持権」や、著作者が誰かを明示させる「氏名表示権」などを含む権利のことで、映画の「著作者」が所有する基本的、かつ譲渡できない権利である。
「著作者」に「著作権」はなくとも、自分の作品を無断で改変させないなど、作り手としての活動の根幹に関わる権利が残されていることは意外と知られていないのではないだろうか。
本来、こういったことは、その道で仕事を継続していくうえで欠かせない知識である以上、例えば映画・映像の学校では基礎教養として必修で教えるべき内容のはずだ。しかし、現状は残念ながら、必ずしもそうはなっていない。その意味でも今回のように法律についての知識を共有する場を作ることは意義深いことであるように感じた。
●自分を守るために、誰かを傷つけないために
「多数の者が明確な取決めもなく複雑に関与し合う状況の中で製作されるに至っており、錯綜した様相を呈している」
裁判の「判旨」にさえこう書かれるほど、この事件の裁判は難航した。その理由は、上述したような映画という表現形態がどうしても抱える権利の所属の複雑さに加え、今回は撮影からソフト化までの経緯のなかで、明確な契約書や覚え書きが交わされることなく、すべてが口約束で決定されていったため、結局「言った、言わない」の水掛け論になってしまったからだ。
現在においても、映画業界で何か物事が進む際に契約書が交わされることは、必ずしも主流とは言えない。大手企業の場合、そういったことに丁寧に慎重に対処する場合がまだ多いが、書類作成に時間や労力、資金を割きにくい中小以下の会社・個人ほど、なおざりになりがちである。しかし、金銭・権利的な確執がおこるのは、むしろギリギリの体制で動く中小以下の映画の現場であるのは想像に難くない。
もちろん、契約書が必ずしも必要な訳ではない。末吉氏は、例え弁護士と言えども、必ずしもすべての仕事に書類を交わしているわけではないと言う。しかし、双方の関係が良好なうちはそれで特別問題にもならないが、一度こじれると、争いが長期化することで、関係者全体が金銭だけではなく精神的にも大きな傷を負うことになるだろう。それを未然に防ぐために契約書というのは、とても有効な手段であることは間違いない。
例えば、これは他の業種では行われていたりもするが、独立映画鍋のサイトで契約書の雛形が手軽にダウンロードできるようにすれば、契約書を交わすことが選択肢のひとつとして選びやすくなるのではないだろうか。そんな提案も末吉氏と映画鍋会員、一般客を交えた対話の中から飛び出した。
自分の権利の輪郭を知ることは、自分を守ると同時に、誰かの権利を知らず知らずに侵害しているということが起きないようにするためでもある。それは、結局自分の立場を守ることに還ってくる。

●映画のための法律相談窓口を作る
会の後半では、客席から多くの質問が末吉氏に浴びせられた。その多くは、実際に映画・映像に関わる立場である来場者からの、実感のこもった問いかけであった。
末吉氏は「映画の作り手など実演家と法律家の壁を取り払いたい」と語る。実際、自分の仕事の契約について何か疑問があっても、「弁護士」を訪ねるのは、なかなか敷居が高い。今回の勉強会は図らずも「法律相談所」の様相を呈したが、独立映画鍋で、日常的に開かれた「法律相談窓口」を設置するべきではないか、その需要は大きいと実感できた二時間であった。
多くの質問のなかで、俳優を職業にしているひとりの来場者から、俳優の権利についての問いかけがなされた。ある仕事での依頼主の対応に激しく傷つき、またそれを法的に訴えることの俳優としてのリスクへの不安を語るその俳優の切実な問いかけは、強く印象に残った。
映画の著作権の話になると、製作者や監督の権利ばかりが語られがちであるが、言うまでもなく映画は多くの人間が関わって成立している。美術にしても、撮影にしても、そして演技についても、それぞれ代替え不可能な技術と感性と個性が、ひとつの映画にはいくつも注ぎ込まれている。法律的には権利者を明確にしなくてはいけないからと、権利はどこかに一元化されるが、スタッフワークの中で多様に発生する「権利」について、効率化を理由に思考停止することなく、汲み取る想像力は失うべきではないだろう。
例えば頻繁に問題となる俳優の肖像権についてもそうであるし、フレームを切り取りRECボタンを押す撮影監督の権利だってあるはずだ。
「権利」の先には、複雑な心を抱える「人間」がいる。私たちは、被害者にも加害者にも、簡単に成りうるのだから、そして映画が集団創作であるからこそ、形式論に陥らずごく当たり前の他者への想像力を持ち続けることが、衝突を回避する基礎にあると改めて考えさせられた。
【文責:深田晃司 写真:野本康夫】